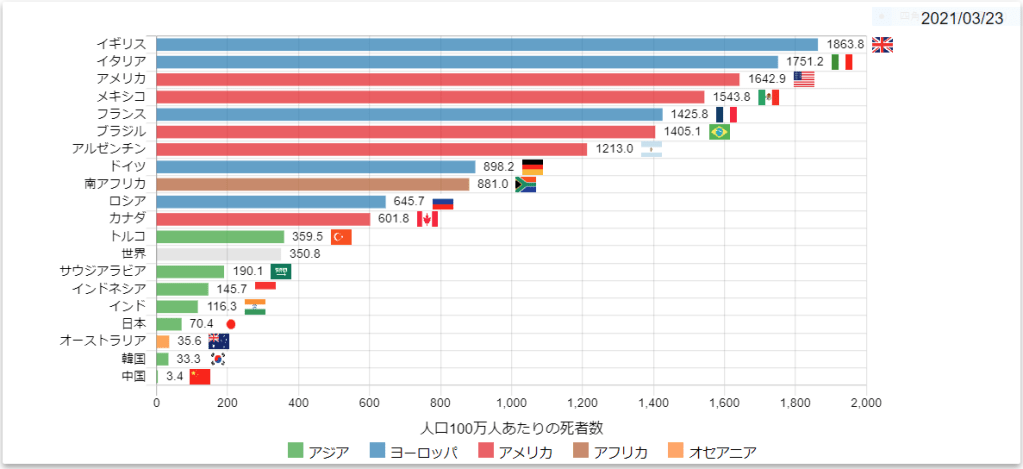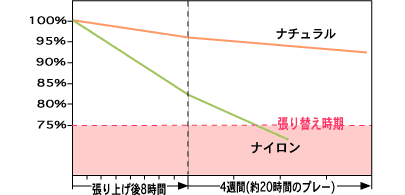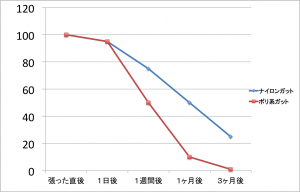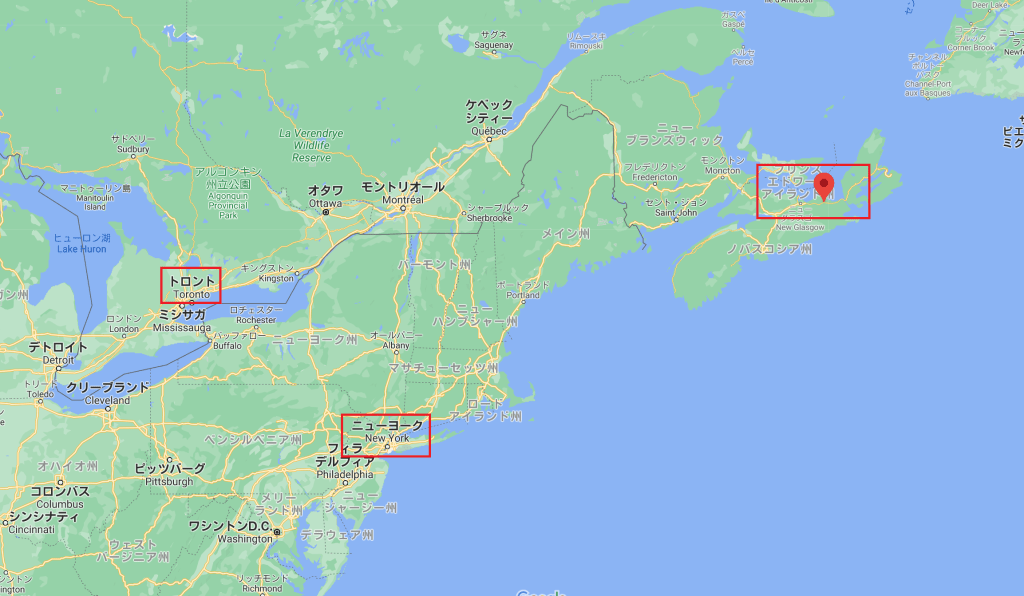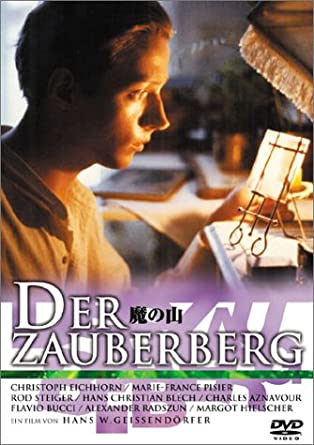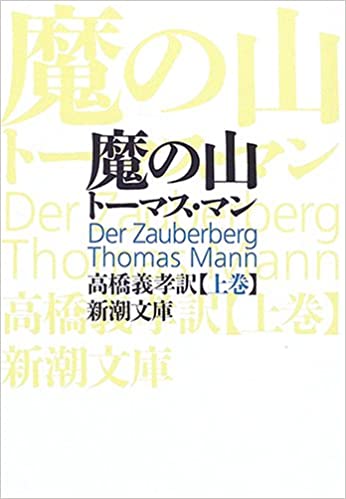< ネタバレの あらすじ >
舞台は、世界中から結核患者が集まるスイスのダボスの高地の《ベルクホーフ》という名のサナトリウムである。
標高1500メートルのダボスには、何十件もサナトリウムがあったらしい
第1次世界大戦の7年前である1907年、24歳のドイツ・ハンブルグ生まれのハンスが、従弟のヨアヒムを3週間の予定で見舞いに訪ねる。ハンスは、造船工学を学んだエンジニアで、造船所で見習いとしての就職が決まっており、気軽な立場で、任地へ赴任する前に見舞いに立ち寄ろうとしていた。ハンスは、この就職前の試験勉強のために、たいへんな勉強をして疲れ果ててしまい、医者からアルプスでの転地療養を勧められ、ヨアヒムを訪ねるところだった。
一方、従弟のヨアヒムは、ハンスより背も高く、肩幅も広い立派な体格をしていた。しかし、実のところ風邪をひきやすく、すぐに熱を出し、ある日とうとう血痰を吐いた。ハンスは、家族の希望通り法律を勉強していたが、やむなく進路を変えて、プロシア軍の士官候補生として採用されていた。ところが、結核の治療のため入院していた。
ハンスは、人生をこれから始めようとする青年であり、ヨアヒムは、一刻も早く病気を治して、軍人としてデビューをしたいと考えていた。
ハンスは、ヨアヒムに教わりながら、《ベルクホーフ》で様々な国の様々な人たちに囲まれて、サナトリウムの生活を始める。サナトリウムの生活水準は、医師や看護師の他に、料理人、給仕たちや門番などが揃って高く、患者の食事は、栄養があり豪華で、日に5度もあり、厳しいが美しいアルプスの高地を散歩をしたり、バルコニーで体を延ばして労わる安静療養の時間など規則正しい生活を送るようになっている。
しかし、バルコニーは隣の部屋とつながっており、患者同士の不倫や情事が密かにおこるなどもあり、根底にある倫理観や道徳観は、1900年ころの当時と、今も変わらない。
そのサナトリウムには、古くからの患者に、30代のイタリア人でフリーメーソン* のセテムブリーニがいた。人文主義者を自称し、代々続く文学者の家系にあるセテムブリーニは、いつも同じ着古した一張羅を着こなす紳士だが、若い二人を見込んで、ヒューマニズム、啓蒙思想、自由、博愛など様々な思想について皮肉交じりにウンチクを語り、ある種、矯正的な感化及ぼそうと語ってくる。
* フリーメーソン:16世紀ころに成立した秘密結社。「自由」「平等」「友愛」「寛容」「人道」を理念とする。
サナトリウムでは、補佐役の医師が、患者相手に「 病患形成力としての 愛 「愛」 誰もが興味深々
療養者にロシア人の若く美しいクラウディア夫人もいた。ハンスは、一目見たとたんに、彼女に恋心を抱く。クラウディア夫人は、夫と別居し、結婚指輪を嵌めず、処々方々の療養地を渡り歩き、ハンスの目には、無作法でだらしのないところがある夫人なのだが、ハンスは自身の自負心と照らし合わせ、クラウディア夫人に対し優越感を覚え、クラウディア夫人の手の平にキスをする夢を見て、甘美な感情に満たされる。ハンスは最初のうちは、クラウディア夫人との関係を休暇中の一ロマンス、遊びぐらいにしか考えていなかったが、それが微妙な関係から生まれてくる興奮、緊張、満足、失望などを感じることで、これが夏の旅行の真の目的へと変わっていく。
ハンスのクラウディア夫人に対する恋心は、ヒッペという男子の同級生に対する好意に類似していた。ハンスは12,13歳のころ、飛び級をしている模範生のヒッペに好意を寄せていた。その感情は、直接にヒッペに分かるように告白するというようなものではない淡いものだった。ハンスは、クラウディア夫人を一目見たときに、ヒッペに再開したような感覚になる。そして、ハンスは、クラウディア夫人に恋心のサインを送りはじめる。そのサインは周囲の人たちに簡単にバレていたが、ハンスの行為は、回りくどいものだったので、クラウディア夫人は知らぬ顔で無視を続ける。
従弟を見舞いに行ったはずの気楽な立場のハンスだったが、彼にも発熱症状があることがわかった。見舞いの立場から、患者としての療養生活が始まる。ハンスは、療養生活がすぐにでも治るものと考えていたが、最終的に第1次世界大戦がはじまるまでの7年間に及ぶことになる。
やっとのことで、二人きりで話ができる瞬間が訪れ、ハンスはクラウディア夫人に跪いて愛を告白する。しかし、クラウディア夫人は「坊ちゃんが、何を言うの。」と取り合わない。この時、ドイツ語やフランス語では男女の間で親しくなってからでないと使わない「君」 「なんて図々しい人なの!」
映画「魔の山」
文学士、啓蒙家で、貧乏なセテムブリーニはやがて、サナトリウムを出て、村人の家の屋根裏部屋でほとんど調度のない暮らし始める。その家の階下には、贅沢な調度品に囲まれて暮らすナフタがいた。ナフタは、オーストリア生まれのユダヤ人だったが、イエズス会* のカトリック教徒に改宗し、出世街道を進んでいたのだが、病気の発病により出世の道が閉ざされていた。 このセテムブリーニとナフタは全く正反対の意見を持っており、セテムブリーニから 「人生の厄介息子」と評されるハンス 二人の話が非常に熱を帯びていて、長いのだが、説得力はない
* イエズス会 資金面で豊かなだが、「イエズス会員」を表す言葉(たとえば英語のJesuit)が、しばしば「陰謀好きな人、ずる賢い人」という意味でも用いられ、近代において、プロテスタント側のみならずカトリック側の人間からも、さまざまな陰謀の首謀者と目されることが多い
セテムブリーニは、ナフタのいないところで、ナフタがいまだにイエズス会に養われている身であることをばらし、悪魔的だと非難する。ナフタは、同じようにセテムブリーニのいないところで、セテムブリーニを、フリーメーソンだとばらし、彼の思想は時代遅れも甚だしいブルジョワ的啓蒙精神と自由思想的無神論であるにも拘わらず、滑稽な自己欺瞞に酔っていると非難する。
二人の議論の一例をあげると、こういう具合である。こうした議論が、延々と果てしなく続く。
「・・・・セテムブリーニはびくともしなかった。ナフタ氏は、と彼は言った。問題は墨で字を書くことではなくて、人類の本源的要求である文学、文学的精神にほかならぬことを百も承知の上でこういうことを言われるのであるが、何とも憐れむべき嘲弄家ではないか!文学的精神とは精神そのものであり、分析と形式の結合という奇蹟であるこの精神こそあらゆる人間的なものに対する理解を覚醒せしめ、愚昧なる価値判断や信念などの力を弱めて解体させ、人類の教化、醇化、向上をもたらすのである。・・・・・」
「ああ、しかし相手のナフタも黙ってはいなかった。彼はセテムブリーニ氏の天使的頌歌(ハレルヤ)を意地悪い、目覚ましい反論をもって撹乱し、あの熾天使のごとく高尚なる偽善の背後に潜むのは破壊の精神であると断じ、それに対してみずからは保守と生命の味方にたつといった。セテムブリーニ氏が声をふるわせて独唱された奇蹟の結合なるものは、要するにいんちきな手品にほかならない。なぜなら、文学の精神は・・・・」
それをハンスは、こう思っていた。
「・・・ところでハンスは自分の哀れな魂こそ彼らの弁証法的争論の主要な対象
軍での出世が約束され、軍に貢献したいと願うヨアヒムだが、いつまでたっても病気が回復しない。とうとうしびれを切らした彼は、回復しない状態で、軍に入隊すると強く決心し、サナトリウムを降り、出発する。 しばらくは、昇進し少尉になったとか、軍隊で元気にやっているといた内容のヨアヒムから手紙がハンスに届くのだが、徐々に軍隊生活が病気によりうまく勤められない様子が伝わってくる。
ハンスは、スキーを初めて履いて一人で冬の山中を彷徨う。最初天候は良かったのだが、突然吹雪き、方向が全く分からなくなる。疲労困憊し、ちょっとした小休止の時に葡萄酒を口にして眠ってしまい、海辺で母と娘や、乙女たちが舞う美しいが性的な夢を見る。やがて夢は、醜い老女が半裸で、幼児を引き裂き、肉片をむさぼり食う場面でハンスは、夢から覚める。彼のスキー行軍は、いつの間にか元の場所に戻るという非常な困難を伴うのだが、ハンスは桎梏からどうにか身をほどき、なんとか奮起して下山する。
ハンスは、スポンサーであるティーナッペル叔父の訪問を受ける。叔父は、ハンスがいつまでこの高地にいるつもりか詰問しにやってきたのだった。しかし、サナトリウムの多くの病人たちや感染状況などを知るにつれ納得するようになり、また、自分が狭量だと思われたくもなかった。ティーナッペルは、サナトリウムで下界ではできないような様々な体験をして、療養中のある夫人の豊満な乳房に魅了されたたり、むしろ下界の生活を送ることが当分の間、完全に間違った不自然な不法なものに感じられるという予感を抱いて恐ろしくなり、ハンスに別れを告げることなく、朝一番の列車で逃げるように帰ってしまう。 これで、下界にはハンスの療養生活を否定する者はいなくなる。
さらに時間がたち、ヨアヒムは、再び病気がひどくなり、母親に伴われてサナトリウムに戻ってくる。ハンスはもちろん、サナトリウムでヨアヒムを知る者たちは、ヨアヒムの帰還を知ってを喜ぶ。
ヨアヒムと彼の母親は、アルプス旅行中の汽車の中で、クラウディア夫人に会い、近く彼女がサナトリウムに戻ってくるということを聞かされていた。母親が、ハンスにそのことを伝え、「とても奇麗な人でした。どこか開けっ放しで投げやりなところがあったけど・・・」と言うのに対して、ハンスは、「あの人には人文的風俗習慣の尺度をもって近づいてはいけない。・・・」と急に饒舌になり、ネガティブな言葉ばかりを言い、母親を驚かせる。
ヨアヒムは、再入院の当初、軍隊生活で男らしさを増したように感じられ、ハンスをはじめとするサナトリウムの面々は喜ぶ。しかし、ヨアヒムの病状は、目に見えて悪化し、やがて食事さえも困難になり、ヨアヒムはまもなく死亡する。呆然とするハンス。ここで物語は、第二部へと進む。
そこへハンスが恋心を抱いているクラウディア夫人がベルクホーフに戻ってくる。ハンスは、軍隊に行っていたヨアヒムから、クラウディア夫人が戻ってくると前もって聞かされていた。しかし、クラウディア夫人は、オランダ人のコーヒー王、ペーペルコルンという老年の男性と一緒に戻ってきた。衝撃を受けるハンス。 しかも、ペーペルコルンは大きな存在感、人間性があり、議論好きなセテムブリーニやナフタをはっきり凌駕する。
もともと慇懃すぎる性格のハンスは、クラウディア夫人をペーペルコルンと争うようなことは全くせず、どんな場面でも王者で、支配者であるペーペルコルンを「人物だ!」と尊敬する。冷淡だったが、どこか肩透かしをされるクラウディア夫人。
ハンスとセテムブリーニ、ナフタ、クラウディア夫人、ペーペルコルンとあと二人、ヴェーザル(ピアノで結婚行進曲を弾くマンハイム生まれの商人・青年)とフェルゲ(ペテルスブルグ出身。高尚な話に向かないと自称する善良な忍従者)の6人は、行動を共にすることが多かった。ヴェーザルは、ハンス同様、クラウディア夫人を自分のものにしたいと思っており、同類と感じてハンスのコートを持ったり、ハンスに対しへりくだった態度をとる。
金持ちのペーペルコルンが費用のすべてを負担して、彼らは、盛大にカード遊びや酒盛りを連夜、遅くまでする。
セテムブリーニとナフタは相変わらず、熱心に哲学的な神学論争を烈しく続けるのだが、ペーペルコルンのいるところでは、いつも彼の存在感の方が上回り、「彼の影響力のために、論争はその決定的に重要だという印象をぼかされてしまい ー こう言っては大変気の毒だが ー 結局こういう議論はどうだっていいのだという印象をみなに与えて
遊びなど、共通体験を深めることで、ペーペルコルンに信頼を寄せるハンスをペーペルコルンも評価する。その長い盛大な酒盛りの深夜、別れ際に、酔っぱらったペーペルコルンは、ハンスがクラウディア夫人に接吻するように求める。「お別れにこの美しい女(ひと)の額に接吻したまえ、お若いお方。」 「いけません、閣下」「あなたの旅のお連れに接吻するなどということは、私にはできないからです。」
ある晩、ハンスは、クラウディア夫人がパトロンであるペーペルコルンが寝ている時間を見計らい二人だけで話をするチャンスを得る。相変わらずハンスはクラウディア夫人を、「君」と呼び、クラウディア夫人は「そういういい方は、問題にしないことにするわ」と応じる。ハンスは、相変わらず、理屈っぽく遠回りにクラウディア夫人に言い寄る。最後に、クラウディア夫人は「あたしはあんたが冷静なのに腹をたてていたのよ。」「あんたがあの人を尊敬しているのを見て、うれしかったわ。いいわ、二人で同盟を結びましょう。」といい、ハンスの手を取り、ロシア風のキスをする。
ハンスは、ペーペルコルンとさらに仲良くなり、いろいろ教わる間柄になる。ある日、病気の老人であるペーペルコルンはハンスに問いかける。( ここが、この小説のハイライト。
「あなたは、一度もマダム(クラウディア夫人)を『あなた』と呼んだことがない。
「あなたには嘘をいいたくないです。ぼくはクラウディアを ー 御免なさい ー 旅のお連れを世間的な意味合いでは交際は全くありませんでした。しかし、ぼくは心の中でクラウディアを親しみを込めて『君』と呼んでいました。ただ、クラウディアがサナトリウムを出ていく前の晩、はじめて親しく話をしたのです。」
「あなたは今でもあの人を愛しておいでなのですね。」
「ぼくはあなたを非常に尊敬し讃嘆しておりますから、ぼくのあなたの旅のお連れに対する気持ちを、ぼくのあなたへの気持ちから言ってどうもおもしろくないのですが。」
「あの人(クラウディア夫人)も同じ気持ちを持っているのでしょうか?」
「ぼくはあの人が今までにそういう気持ちを持ったことがあるとは申しません。ぼくにはむろん女性に愛されるようなところはあまりありません。ぼくにはどんな人間的な大きさがあるでしょう。
「それにしても、私があなたに自分では知らずに与えた苦しみは、たいへんなものたったに違いない。」
ハンスとペーペルコルンの熱のこもった会話は続く。
ハンスは、病気により長くサナトリウムに留まり世間と縁が切れてしまい、死んだも同然で、クラウディアへの理性を失った愛情表現も病気に屈服したからだ お互い『君』と呼び合う兄弟になろうと申し出る
仲の良い6人は、2頭の馬車を仕立てて森と峡谷の中にある滝へピクニックに出かける。
その途中、同じ馬車に二人で乗るヴェーザルはハンスに言う。「あなたは今では、ペーペルコルンが出てきて、おかしなことになっているが、一度はうまい巡り会わせで楽園に遊んでクラウディア夫人の腕を頸に巻き付けられたことがあるから、わたしに対して上から目線なんです。」「私は、クラウディア夫人に、もう、ぞっこんです。私がどんなに彼女に焦がれ飢えているか、しかもその思いが遂げられずに我慢していなければならないか、その苦しみはとても言葉ではいいあらわせません。・・・。」とハンスにこぼす。
滝では、ペーペルコルンがワインを何杯も飲みながら、立ち上がって口を動かすのだが、何を言っているのか誰にも理解できないものの、全員がその存在感に圧倒され、頷きながら頭を縦に振って納得していた。やがて、ペーペルコルンは出発を命じた。
そのピクニックの晩、ペーペルコルンは、象牙を使いコブラの歯を模し、毒を入れた注射器で自殺する。その夜、よく眠れなかったハンスは、深夜2時、クラウディアに呼び出されペーペルコルンが自殺した部屋で二人で話をする。
「この人は私たちのことを知っていたのかしら。」とクラウディアが言う。「この人は、ぼくが君にキスをしなかった時に、万事察してしまったのです。いま、この人が言ったとおりにするのを許していただけないでしょうか。」とハンス。クラウディア夫人は目を閉じて、彼の方へ顔を差し出した。ハンスはその額に唇をつけた。
ハンスは、ペーペルコルンとクラウディア夫人を失い、完全に行き詰まっていた。ハンスの顔は、ヨアヒムが自暴自棄な反抗を固めはじめたころに見せた顔つきを、はっきりと思い出させた。 ハンスは、自分の周囲を見渡した。周囲のものは、時間のない生活、心配も希望もない生活、停滞していながらうわべだけは活発に見える放蕩な生活、死んだ生活だった。
ベルクホーフでは、あらゆる慰みごとが流行っていた。写真の現像、切手の蒐集、チョコレートをむさぼり食う、目をつぶってブタの絵を描く、数学、トランプなど、ハンスもこられに夢中になる。 ハンス自身、自分の身に巣くう「恐ろしい鈍感」に慄然とする
サナトリウムに突然最新鋭の蓄音機が設置させる。その蓄音機は最高級品であり、素晴らしい音を出した。また、200枚以上のレコードがあり、最高峰の楽団が演奏していた。療養者全員が夢中になるのだが、ハンスはその蓄音機の操作者になることを買ってでる。そして、一人でもその音楽を楽しむ。ハンスが好きだった曲は、オペラ、「アイーダ」。これを味わった後にドビュッシーの「牧神の午後」を聴いて息抜き。その次が、オペラ、「カルメン」。グノーのオペラ、「ファウスト」の中の「祈り」の歌。最後にシューベルトの「菩提樹」の「泉のほとりに」。 ハンスは、この「菩提樹」の中に希望を見出す。
ベルクホーフでは補佐役の医師が研究結果を講演で発表していたが、やがて神秘的な世界へと入り込んでいく。若い生娘を霊媒にしてこっくりさんに熱中する。生娘には霊が取りつき、死者を呼べる。ハンスは、ヨアヒムを呼び出すよう依頼する。不思議な現象が様々に起こる。
ベルクホーフは、毒々しい口論、憤怒の爆発、名状しがたい苛立ちに支配されるようになる。 最近入所した反ユダヤ主義者は、ユダヤ人の入所者と悪童のような取っ組み合いから、誰も見たことがないような死に物狂いの喧嘩をする。
また、ポーランド人の間で、名誉棄損事件が起こり、お互いが非難する文書を入所者にばら撒いていた。これを受け取ったセテムブリーニとナフタの二人は、決定的な口論に発展し、ナフタはついにセテムブリーニに決闘を申し込む。これを受けるセテムブリーニ。何とか翻意させようとするハンス。
しかし、二人は翻意せず、ピストルを至近距離から撃ちあう決闘を行う。フェルゲとヴェーザルが介添え人となり、ハンスは立会人となる。15歩離れたところで、お互いが向き合い、3歩ずつ前進し、ピストルを互いの胸に向けあう。その時、セテムブリーニは空に向けて何発かは発射する。「あなたは空へ向けて発射された。」怒るナフタ。「どこへ撃とうと私の自由です。」「もう一度うちたまえ。」「そのつもりはない。さあ、あなたの番だ。」 ナフタは「卑怯者!」と絶叫し、自分の頭に弾丸を打ち込んだ。
ハンスは、サナトリウムでは人畜無害な人物であり、放置されるようになっていた。自由と呼んでよいのか放恣(気儘で節度がない)なのか。
しかし、このとき轟然と世界がどよめき、青天の霹靂がとどろいた。オーストリア・ハンガリー皇太子銃撃事件を契機にする第1次世界大戦の勃発である。セテムブリーニは、決闘事件以来、呆然自失となり無気力だったが、破局へ向かうヨーロッパの運命とともに複雑な心境だった。
ベルクホーフは、母国へ降りていこうとする人たちで混乱していた。ハンスもそうだ。セテムブリーニは、ハンスを駅まで見送り、「あなた」と呼びかけるのを止め、「ジョヴァンニ」(Giovanni)と「君」と何度も呼びかける。「私は君がもっと違った形での出発をするところを見たかった。でも、いいでしょう。・・・勇敢にお戦いなさい。さようなら。」
ジョヴァンニというのは、モーツァルトのオペラ「ドン・ジョヴァンニ」からきている呼びかけで、「色男!」的な親近感を表す呼びかけだろうと、主は思う。
ハンスは、3千人の増援部隊の一員として、戦場にいた。彼らはすでに甚大な被害を被っていたが、目的地まで戦わなければならない。弾丸が当たり、額を、心臓を、腹部を撃たれ、腕を伸ばしながら倒れる、顔を泥の中に伏せて横たわる戦友の間を、よろめきながら突進していく。生存を期待できない悲惨な戦争である。
一番最後の部分を写し取ると、・・
「君は『鬼ごっこ』によって、死と肉体の放縦との中から、予感に充ちて愛の夢が生まれてくる瞬間を経験した。この世界を覆う死の饗宴の中から、雨の夜空を焦がしているあの恐ろしい熱病のような業火の中から、そういうものの中からも、いつかは愛が生まれてくるであろうか?」
(あらすじ終わり)
上巻は、物語がゆっくり、どこか牧歌的に展開し、下巻ではピッチを上げて、異常事態が短いインターバルで頻発する。最後には、第一次世界大戦が起こり、ハンスが病気をおっぽりだして、ドイツ軍の作戦に加わる。他の患者たちも、出身国の兵士となるべくサナトリウムを我先にと飛び出し帰国する。物語は、ハンスの生死も不明な状態で終わる。戦争は、これまでの病死や喧嘩、自殺などとはるかにスケールが違う。
翻訳が、率直に言うと、読みにくい。一般に意味が通じない日本語表現が、かなり出てくる。例えば、「あなた」と「君」という表現の違いは、ドイツ語やフランス語の二人称が親近度や長幼で変化するのだが、読者向けに補足説明があったら親切だろう。
おしまい