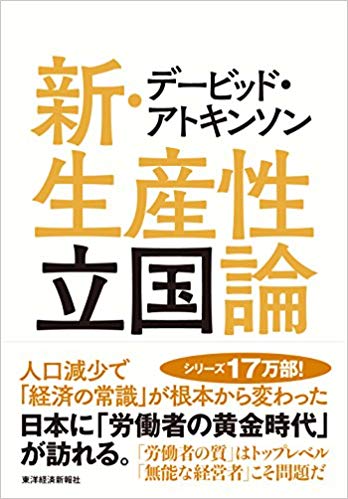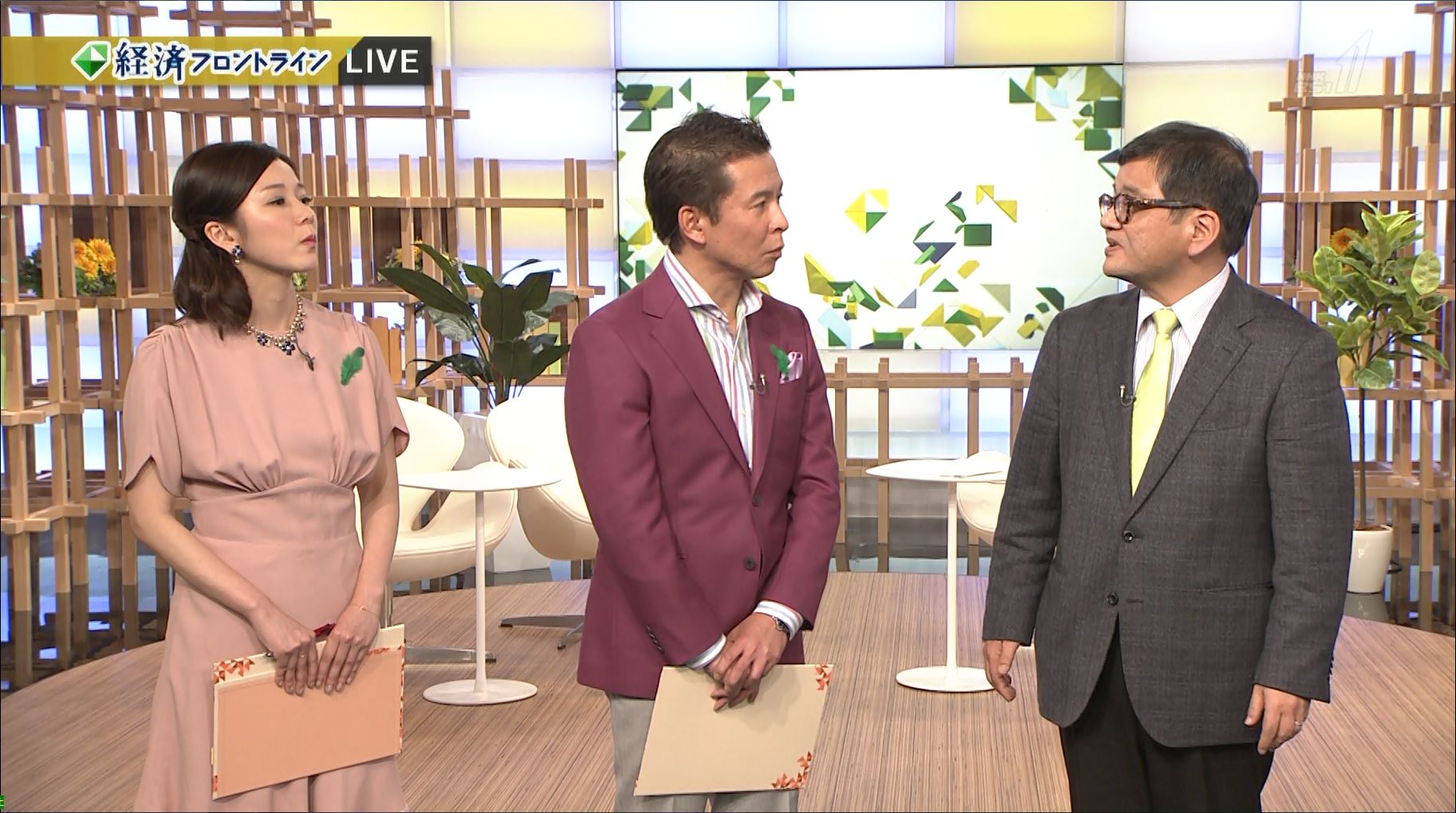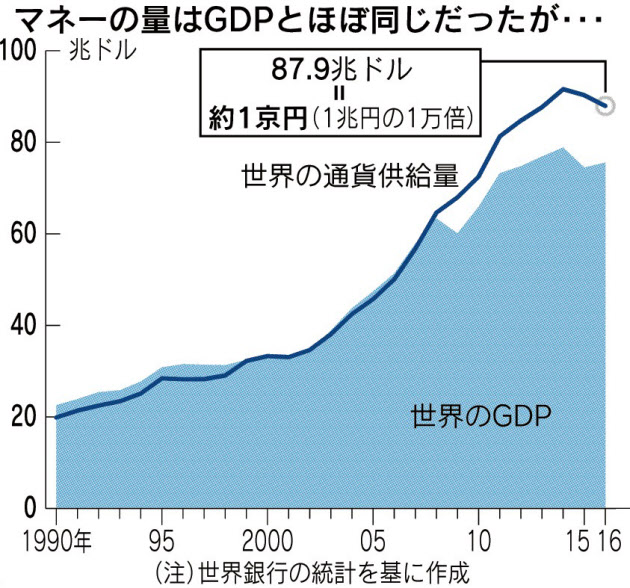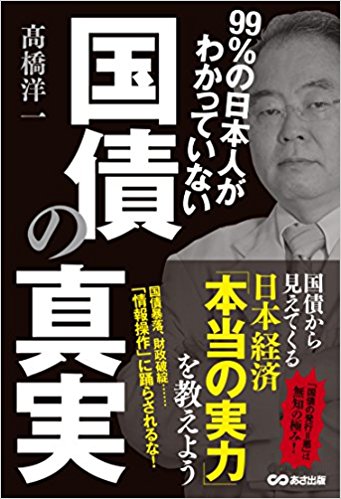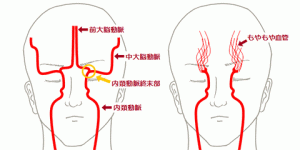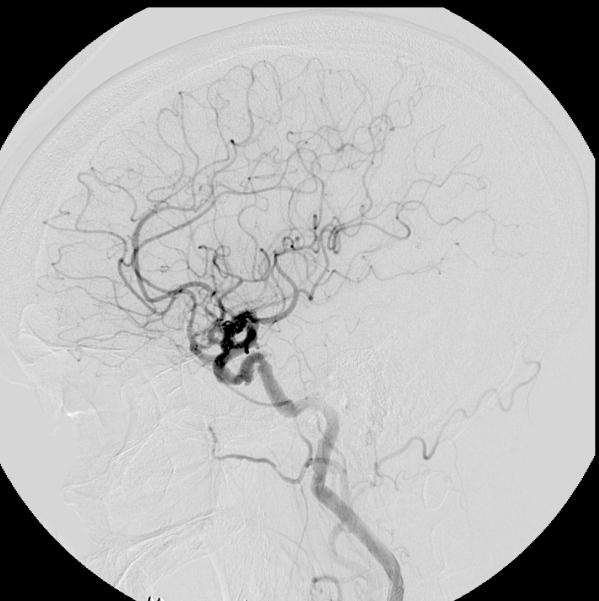青山学院大学教授で日本のグールド研究の第一人者の宮澤淳一氏は、「グレン・グールドはクラシックの音楽家ではない」と言う。http://www.walkingtune.com/gg_07_kangaeruhito.html 氏は、「グールド本人が意識していたかどうかはともかく、彼の演奏はクラシック音楽での解釈の約束事を無視した営為であって、これは作曲家よりも演奏家の創意が重視されるジャンル(ジャズやロック等のポピュラー音楽)でこそ輝く個性である。だから、異端視するよりも、『グールドはクラシック音楽ではない』と考えた方がすっきりする。」と結論づける。 この発言は、もちろんデフォルメした言い方でグールドはクラシックの音楽家なのだが、グールドだけが他の演奏家と比べるとまったく違った考え方をしているという意味で、とても分かりやすい。

クラシック音楽の世界では、作曲家が王様であり、演奏者は作曲家の家来という構図であり、演奏家は如何に作曲家の意図を忠実に再現することができるかが、この業界の指標となっていた。楽譜に忠実に演奏することに加えて、作曲年代と楽器の制限(例えば、現代のピアノの性能はロマン派の作曲家の時代と性能が異なっている)を考慮する古楽器ブームもある。バッハの時代にピアノはなかったし、モーツアルト、ヴェートーベンの時代のピアノも今のピアノに比べるとちゃちで、当時の楽器で忠実に再現したらという考えは今でもある。音楽を楽しむことより、方法論を優先する、言ってみれば原理主義が幅を利かしている。
時代とともに楽器そのものが変わり、作曲家たちも新しい語法で作曲し、オーケストラの規模は大きくなり続け、行き着いた極限がマーラーだと言われる。
主は、最近読売交響楽団(井上道義指揮)が演奏するそのマーラーの「千人の交響曲」のコンサートへ行ってきた。この「千人の交響曲」はオーケストラ自身の各楽器の構成数が大きいのもあるが、パイプオルガンが使われ、ハープが何台も並び、チェレスタ、トライアングル、マンドリン、ソロ歌手8人に加え、大人の合唱団200人以上、子供の合唱団50人以上が加わる。第1部と第2部を合わせて90分ほどある大曲なのだが、手を変え品を変えさまざまな旋律を楽しむことができ、あっという間の90分で大いに感動した。しかし、感動の仕方が、ピアニッシモとフォルテッシモの落差のスケールに圧倒されるという面が確実にあり、「こりゃあ、一種のスポーツだな。何の哲学も感じられないな」とも思ったし、「やっぱ、ヴェートーベンの方が深いな。シェーンベルクの方がカッコ良いな」とも感じた。当り前だが、音楽は時代を下れば良いものになるとは限らない。
グールドの音楽の演奏態度は、音程以外、どのクラシックの音楽家誰もが金科玉条とする作曲家の指示を守らない。楽譜の強弱記号、速度記号、反復記号を守らない。常に守らないわけではないが、自分の判断を優先する。音符の装飾方法も業界の概念を覆して独自な面があるらしい。和音を和音として同時に打鍵することはほとんどなく、10本しかない指で3声、4声を際立たせる。モーツアルトは「クリシェ」(紋切り型でありきたり、新しいものがない)だと批判して、世間に対して挑戦的になり、「こうしたら面白くなるぞ」と上声のメロディーだけだったところに内声の音符を加えポリフォニックに改変した。グールドには作曲家への指向が常にあり、どの曲もその持つ曲の本来の良さ、作曲家さえ知らなかった良さを、従来の演奏方法・観念に囚われず示そうとした。
音楽家は普通、師匠に師事し師匠の言う事を絶対として受け取り、業界の固定観念の中で生きるのが常だ。有名な音楽家への道は、コンクールで優勝することだ。そうして名を知られ、コンサートツアーへ年に何百日も巡る。コンクールで優勝するためには、多くの審査員からまんべんなく票を得る必要があり、優れた感受性や斬新さよりも、そつなくこなす技術が求められる。当然、曲の解釈も個性的なものより平均的で新味がないものになる。こうしてどんな名曲に対しても、ありきたりで、平均的な演奏をする演奏者が再生産されるシステムが出来上がる。
ところがグールドの両親は、コンクールで優勝するための競争は息子を消耗させると考え、コンクールに息子を極力出さないようにし、グールドは自由に自分の頭で音楽を考えるように育った。グールドは母親に10才までピアノを教わったが、やがて母親が教えることができないレベルになる。案じた母親は、10才から19才までチリ人のピアニスト、アルベルト・ゲレーロが教えるように手配した。ゲレーロは生徒に子供を取らない主義だったが、グールドのレベルの高さにすぐ気づき生徒に取ることを引き受けた。ゲレーロに言わせるとグールドは “Unteachable” な生徒だったという。教えようとすると猛烈に反発するために、答えを自分で発見させるように仕向け、単に教えられるよりも自分で発見させるほうがグールドにとってより活性化できると考えたという。プロデビューを果たした後、ゲレーロから大きく影響を受けたのは明らかだったにも拘わらず、グールドは「ピアノは独学でした」と言い張りゲレーロは落胆したが、「それでいいんだ」と落胆したそぶりを見せなかった。
ピアノは打鍵した後、鍵盤を押さえている間、打鍵された音が減衰しながら続く楽器だ。ピアニスティックとかピアニズムという言い方があり、いかにもピアノらしく響かせるという意味なのだが、メロディーをレガートに音価(音の長さ)一杯に引っ張り、メロディーと伴奏をゴージャスに、流麗に弾くのがピアニスティックな演奏である。ところが、2回目のゴールドベルグ変奏曲の録音に関する1982年のティム・ペイジ(TP)との対談では、グールド(GG)は自分の奏法に関して次のように言っている
(GG)「・・僕が大バッハを扱う時の音のコンセプトは、また例の言葉をあえて使うなら、デタシェ(=音と音がつながらない、隙間がある)なんだ。つまり、ふたつの連続した音の間のノン・レガートの状態そのものや、ノン・レガートの関係、ないしは点描画法的な関係が基本なのであって、これが例外的な奏法ではない。むしろ例外的なのはレガートでつなげることなんだ」
(TP)「もちろん、君の主張がピアノ奏法の大前提を覆すことになる点は承知しているよね!?」
(GG)「うん、結局そうしようとしているんだ」(翻訳:宮澤淳一)
このデタシェという言葉はフランス語なのだが、英語は “Detach”(=de-touch 切り離す、分離させる)、名詞形は “Detachment” である。
この”Detachment” が、夏目漱石の小説「草枕」に出てくる。グールドは、「智に働けば角が立つ。情に掉させば流される。意地を通せば窮屈だ。兎角に人の世は住みにくい。 住みにくさが高じると、安いところへ引き越したくなる。どこへ越しても住みにくいと悟った時、詩が生まれて、画が出来る」という名文で始まる「草枕」をこよなく愛した。冒頭から芸術と世俗、非人情と人情の対比をして、漱石の「芸術とは何か?」が語られる。「住みにくき世から、住みにくき煩いを引き抜いて、難有(有難)い世界をまのあたりに写すのが詩である。画である。あるは音楽と彫刻である」と言う。人情を「苦しんだり、怒ったり、騒いだり、泣いたりは人の世にはつきものだ。余も30年の間それを仕通して、飽き飽きした」と言い、これに対して、超然としているさまを漱石は「非人情」と言い、「非人情」の訳語に翻訳者のアラン・ターニーは “Detachment” を使った。「・・・淵明、王維の詩境を直接に自然から吸収して、少しの間でも非人情の天地に逍遥したいからの願。一つの酔興だ。 勿論、人間の一分子だから、いくら好きでも、非人情はそう長く続く訳には行かぬ」と言う。グールドは「草枕」を二十世紀小説の最高傑作のひとつだと愛してやまず、従妹のジェシーに電話で全文を読み聞かせたり、晩年にはラジオで「草枕」を朗読する番組を作ったほどで、死後グールドの部屋には多くの書き込みがされた何種類もの「草枕」の翻訳本があり、脚本を書こうとしていたという。
このデタシェの点描画法は「非人情の天地に逍遥」することであり、緊張の弛緩、軽妙なユーモアだ。逆に、レガートは緊張を高める。グールドは、複数の旋律があるポリフォニックな曲では、旋律にデタシェとレガートを弾き分けており、時に交代させ飽きさせない。一般的なピアニストの場合はレガートが基本で、美しく緊張を保つものの一本調子となり飽きてくる。
グールドは、ポリフォニックな対位法で書かれた曲を好んだ。また、子供時代にオルガンを学び足でも旋律を弾くことで、和音であっても自然と和音を分解し、別のメロディーとして捉える。ピアノで各声部を弾くとき、あたかも弦楽四重奏を演奏するように別の楽器が鳴っているように演奏していた。
普段の生活でも、コンピュータ用語を使えばマルチタスク人間だった。レストランでは、近くの席の複数のテーブルで交わされる3つか4つの会話を同時に理解できた。テレビでドラマを、ラジオでニュースを流しながら、スコアを頭に入れ、どれも理解できていたという。彼は対位法的ラジオと言われるドキュメンタリーのラジオドラマ、極北で暮らす人々の孤独をテーマにした「北の理念」などの「孤独三部作」を作ったのだが、5人の登場人物が全く違う内容を語る話声をフーガのように合成したもので、誰も話の内容を理解できないとの批判もあったが、グールドは「私たちの大半は、自覚しているよりもはるかに多くの情報を取り入れる耳を持っている」とライナーノーツに書く。後にはこのラジオドラマのTVバージョンも作られる。
グールドは、誰でも知っている有名な曲は、特に確信犯的にこれまでになかった演奏をした。バッハの平均律クラヴィーア曲集第1巻第1曲のプレリュードは有名で、ググってみたら大和ハウスと資生堂がCMに使っていた。この有名な曲は、どのピアニストも流れるように優しく美しく弾くのが普通だが、グールドはやはりスタッカートで弾き、度肝を抜いた。変っているが、この曲がもつ良さは伝わってくる。 ベートーベンのピアノソナタ「月光」、これも第1楽章は特に有名だろう。(大和ハウスはクラシックが好きなようで、この曲の第3楽章をCMに使っている)こちらは感情を思い切りこめスローテンポでドラマチックに弾くのが普通なところ、グールドはアップテンポで抑揚をつけず淡々と同じリズムで弾きとおす。それが新鮮で、逆に清潔、潔癖、秘めた激情を感じさせる。 モーツアルトで有名な曲と言えば、「トルコ行進曲」だろう。この「トルコ行進曲」はピアノソナタ第11番の最終楽章なのだが、やはりグールドは破天荒な演奏をしている。下の写真は、「グレン・グールド・オン・テレヴィジョン」に収録されている1966年に行われたハンフリーバートンとの対話だ。この番組でグールドは、自分の音楽観を披露しながらピアノを弾く。これが実に刺激的だ。ごく一部だが、YOUTUBEにその様子アップされていたので、再生していただけたら嬉しい。また、「トルコ行進曲」聴き比べというのもあり、ギーゼキング、グールド、グルダ、バックハウス、ホロヴィッツが並んでいるのだが、グールド以外は軽快な元気さだけが伝わってくるくるのみだ。グールドはこの「トルコ行進曲」を断然ゆっくりと、初めは控えめに弾き始め、徐々に抑揚をつけメロディーの音色を変え、変化を楽しませてくれる。伴奏の和音をことさら崩して弾き、やはり抑揚をつけクライマックスを最後に持ってきているのが良く分かる。主は大いに感動してしまった。

ちょっと長くなってしまったが、この番組の中で、他にもグールドは面白いことをいくつか発言している。自分は偏屈だったので、誰でも練習するこのピアノソナタを弾いたことがなく、どのように弾くか1週間前までアイデアが決まらず、スタジオに入ってもまだ確信がなかった。また、すでに立派な演奏が残されているので、それと同じ演奏をするのではなく、違った演奏をするのが演奏家の務めで、それが出来なければ職業を変えるべきだとまで言っており、次回にでも紹介したい。
おしまい