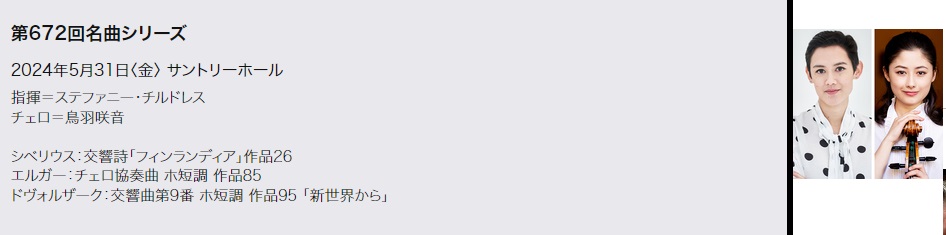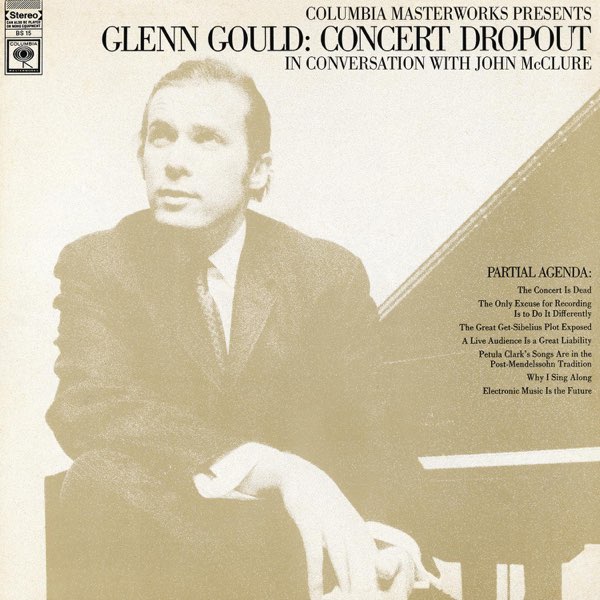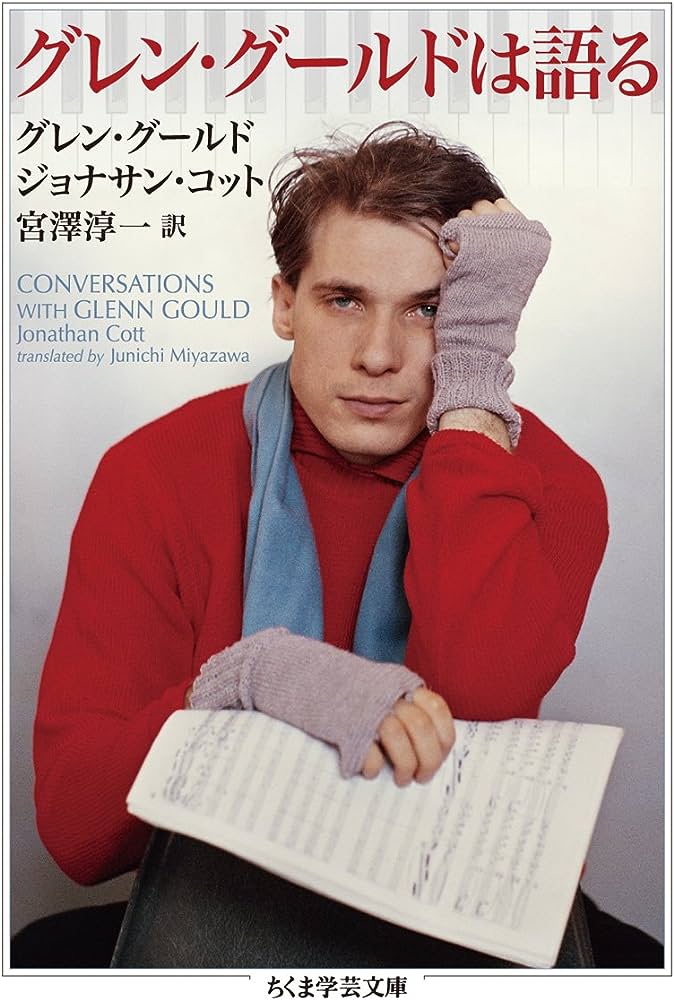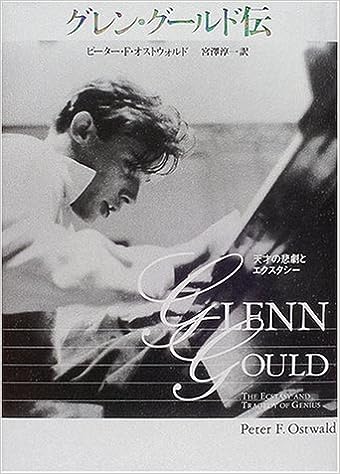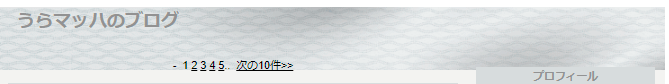— 2023/8/11 一部修正しました。—
NHK放送にピアニストの清塚信也さんと歌手でモデルの鈴木愛理さんがMCをつとめる《クラシックTV》という毎週放送の楽しい音楽番組がある。この番組で「ピアニスト グレン・グールドの世界」が放送された。最初は、2022年だったようだが、親爺が見たのは、2023年5月にあった再々放送だった。
NHK・クラシックTVのHPから
https://www.nhk.or.jp/music/classictv/482351.html ☜ こちらが、そのNHKの番組のリンクである。
この番組の呼び物は何といっても、清塚信也さんが実際にピアノを弾きながら、その日の取り上げた音楽を楽しく解説してくれるところにある。ご存じのとおり清塚信也さんは、超売れっ子のピアニストであるだけでなくトークが楽しい、バラエティー番組にも引っ張りだこの方である。
プロのピアニストがピアニストを正面から批評することはなかなかしないものだ。そうすれば、自分の力量と対象のピアニストの力量の差を意識したり、往々にして、嫉妬心などがおこり、はっきり物を言わないのが普通だ。しかし、グールドは没後40年を超えるピアニストでもあるが、清塚さんは極めて率直で公平、説得力のある説明をされており、そこにこの番組の楽しさの秘密があるのだろうと思う。
ところで、クラシック音楽の世界も弱肉強食の世界だなと、しみじみ親爺は思う。というのは、この番組MCの清塚信也さんとクライバーン・コンクールで優勝した盲目のピアニスト辻井伸行さんのお二人は、ほぼほぼコンサートのチケットの宣伝を目にしたことがない。つまり、それは宣伝をしなくてもチケットが売れてしまうのだと思う。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
親爺はこの番組をNHKプラスで録画した。そうであれば、YOUTUBEにアップしてこのブログに張り付ければ、その内容を、一番正確に分かりやすく皆さんに共有できるのだが、それは著作権の問題が生じる。 ついては、申し訳ないですが、このブログに文章にして書きますので、それを読んで判断してください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
では、ここからその番組の内容を説明する。次の写真は、司会の清塚さんと、ゲストでタレントのハリー杉山さんである。ハリー杉山さんは、お父さんがイギリス人、お母さんが日本人で、子供の頃にチェロをやっていたそうだ。彼が言うには、「オカンがグールドが大好きだった!」ということで、非常に的確なコメントをされる。
1.ノンレガート奏法は、べつに簡単じゃない
この番組の冒頭は、清塚さんがグールドの演奏を真似るようにバッハの平均律クラヴィア曲集第1巻第1曲の有名なプレリュード(前奏曲)を、一音一音、音を区切りながらノンレガート(スタッカート)で弾くシーンから始まった。グールドは、この有名な曲をノンレガートで弾いたのだが、この曲をノンレガートで弾いたプロのピアニストは、他にいないだろう。このノンレガートの演奏方法だけでなく、真夏でもオーバーコートを手放さず厚着をしているとか、食事に関心がなかったとかグールドを特徴づける《エキセントリック》
そもそも、グノーはこのバッハのこの曲を伴奏に用い、有名な歌曲「アヴェ・マリア」を作っているほどで、普通は思いっきりなだらかで滑らかに演奏して、ノンレガートでは演奏しない曲である。
VIDEO
【noboru 1947-3から】バッハの作曲、グノーのアレンジの「アヴェ・マリア」 とても良いです! グールドは、この曲をノンレガートでコミカルにさらっと弾き、リスナーを驚かした。しかし、この曲がもつ美しさや穏やかさはまったく失われておらず、非常に新鮮に聴ける。
清塚さんが弾いたノンレガートのこの曲は、ピアニストが普段このような弾き方をすることがないことを窺わせる。つまり、ちょっと批判めいて言いにくいが、音の粒が不揃いで、たどたどしく苦しいものがある。変な表現だが、グールドの弾くノンレガートのこの曲は、ノンレガートなのに滑らかでレガートでもあるように聴こえる。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ところで、グールドは、世間によく知られた有名な曲ほど、《エキセントリック》
もっともモーツァルトのピアノソナタの場合は、どの曲も一般的な演奏から外れた挑発的なものだ。とはいうものの、グールドが《ビタミン剤を注入した演奏》[1] はとても説得力があり、違和感がない。むしろ、オーソドックスな演奏は平板に思えてくるほどだ。
[1] 英国のクラシック音楽テレビの司会者であるハンフリー・バートンとの対談で、グールドは、「モーツァルトのピアノソナタの内声部に、曲が良くなるかどうかは別にして、対位旋律をポリフォニックに加え、《ビタミン剤を注入》することをためらわない。」という意味のことを語っている。
2.清塚さん「腕の力じゃなく体重を乗せて弾くことで、ふくよかできれいなフォルテが出せる。ピアノの基本中の基本です。」
ピアニストがフォルテを弾くときの基本は、「手だけで鍵盤を叩くのではなくて、腕全体に体重を乗せて鍵盤を弾くことで、ふくよかで綺麗なフォルテが出せる。これがピアノを弾くときの基本中の基本です。」と清塚さんは言う。ところがグールドは、この基本中の基本を嫌がり、ピアニストから完全に逸脱している。
彼は、椅子の脚を短く切ったこのピアノ椅子を生涯使い続け、どこへ出かけるにも《愛犬》のようにこの椅子を持ち運んだ言う。このような低い椅子に座り、おまけに椅子をこれ以上に低くすると脚を自由に動かせないので、さらにピアノを数センチ持ち上げて演奏した。この結果、手首が肘より上に来て、ピアノの鍵盤に体重をかけて弾く、普通のピアニストとはまったく違う弾き方(とても褒められない姿勢)になっているという。グールド自身も、この座り方のために本当のフォルテッシモを出せない欠点があると認めている。[2]
清塚さんは、バッハのパルティータ第2番の冒頭のシンフォニアを、思いっきり猫背で顔と鍵盤を近づけ、唸り声も出しながら、グールドを真似つつ弾く。スタジオは、《苦笑》という感じの笑いに包まれる。
清塚さん 「(グールドは)強く弾く、大きく弾くという、フォルテというものにあまり興味がなかったのかもしれない。」
ハリー杉山さん 「ということは、フォルテというものに彼なりの美しさを感じられなかったということでしょうか。」
清塚さん 「そうね、もしくはフォルテと言っても・・・」と言いながら、同じ和音をはるかに小さい音でピアノを鳴らしながら言う。
清塚さん 「もっと繊細な音をさらに弱く弾くとか」と言いながら、普通のピアニストより小さい音のフォルテを最大の音の基準にして、「ピアノ、ピアニッシモをもっと小さい音量で表現したのではないか。」と言う。
さらに清塚さん 「(グールドの)特徴としては、このような弾き方をすることで、一つ一つの音をはっきり弾き、指でものすごく、この音ソなら、ボリュームの5で弾き、ラの音はボリュームの6で弾く、というように一個づつの音すべてをコントロールしようとしたのではないでしょうか。だから、大雑把にガーっと行く演奏ではなくて、一個づつの音を全部コントロールして、自分のところで支配していたいっていう現れなんじゃないか。」
ハリー杉山さん 「まるで譜面以外に、ボリュームの譜面みたいなものが、違う次元で見えているかのように聴こえてきますね。」
[2] 「グレン・グールド発言集」(PL.ロバーツ編・宮澤淳一訳 みすず書房)の1959年「私は自然児です」の対談のなかで、トロントのジャーナリスト、デニス・ブレイスウェイトに語っている。
3. 革命的な演奏スタイル《ポリフォニー》を弾く難しさ
清塚さんは、ポリフォニーについて説明する。
清塚さん 「ポリフォニーっていうのは、メロディーに対して伴奏ではなくて、メロディーに対してメロディーがくる。右手がメロディーをやってれば左手もメロディーをやっているという状態のことで、非常に演奏するのが難しい。」
バッハのパルティータ第2番の終曲の第6曲カプリッチョの冒頭部分を弾く。右手の旋律に続いて、左手の旋律が遅れて入ってくる。
清塚さん は、この曲を右手の下降する旋律が始まった後、左手の旋律が上昇しながら入ってくるところを弾き、「これだけ、右手だけ弾いていても凄く難しい。ここで、左手が入ってくる。(左手が)追いかけてくるんですね。左手のクレッシェンドに、右手が一緒に乗っかっていくと、二人で弾いているように聞こえない」
清塚さん 「ここを明確に弾くのはすごく難しいんです。右手は下降しながらデクレッシェンドしていき、同時に弾かなければならない左手は上昇していき、クレッシェンドしないといけない。(右手が)一緒にクレッシェンドしちゃうとつられている感じになる。これをバッハだけじゃなくてあらゆる曲にほどこした。」
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ここで親爺は思う。この清塚さんのパルティータを使った説明の例は2声なのだが、グールドが最も好きだったフーガは4声とか、多いものでは5声で書かれた曲が普通である。こうした多声の曲を10本の指しかない一人で、声部を分けながら弾くのは非常に大変である。
グールドは、フーガを弾くときに弦楽四重奏者(第1ヴァイオリン、第2ヴァイオリン、ビオラ、チェロ)が頭の中で演奏しているようにピアノを弾いていると言っている。しかし現実問題として、フーガであっても4声以上の声部が同時に鳴っているのは少なく、4声の曲でも一つの声部は休止して、実際に同時に鳴っているのは3声ということが多いだろう。逆に、聴く方としても、あまりに多声が同時に鳴るより、声部にメリハリをつけて交代しながら、3声ほどが鳴っている場面の方が聴きやすいということもあるだろう。
ところが、実際の弦楽四重奏団の団員4名がフーガを演奏する場合、どの奏者も自分の義務を十分以上に果たそうとしてずっと音量を下げずに弾き、聴いている方は「暑苦しいなあ」、「ごちゃごちゃしているなあ」と感じがちである。そういう意味では。グールドが自分の解釈で各声部の主役を交代させながら、曲想にも声部にも、メリハリをつけて弾くというのが、非常に聴きやすい。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ここでグールドが、モーツアルトのピアノソナタの楽譜を書き換えたという話題へと展開していく。グールドが弾く、モーツァルトのピアノソナタ第13番第3楽章が映し出される。ところで、グールドは、『モーツァルトはいかにダメな作曲家になったか』 というTV番組をツアー引退後の1968年に作り、それはそれは過激で強烈にモーツァルトをこき下ろしている。その番組は、グールドのこの曲の全曲演奏で締めくくられるのだが、それがまた活力があり楽しく本当に素晴らしい。おそらくグールド自身もうまく弾けたと思っていたんだと思います。
ハリー杉山さん 「(普通の演奏と比べて)踊っているというか、ユーフォリア(多幸感:euphoria)の幸福感が増し増しになった ような気が・・・・」
清塚さん 「だから伴奏じゃなくて、すべてが意味のあるメロディーなんだ と、全員が主役のセリフを言っているみたいな 雰囲気にモーツァルトをしたかったのかなあという感じもあります。」
4.4人のピアニストのグールド観
(1)ランラン(中国出身の有名なピアニスト・1982年生まれ41歳)
「10歳のとき、グールドが弾くゴルトベルク変奏曲のアリアの映像を見たことを今も覚えています。その美しいサウンドを聴いて、怖がらずに自信を持って自分のイメージを膨らませて演奏すれば良いと教わった気がします。数年前、私なりのゴルトベルクのレコーディングが出来たのも偉大なグレン・グールドのおかげです。最も偉大なグレン・グールド!!(”Greatest Glenn Gould !!”)」
(2)小山実稚恵(1959年生まれ・1982年チャイコフスキー・コンクール3位1985年ショパン・コンクール第4位)
「一番のグールドの音楽の魅力はそこに喜び があることだと感じています。グールドの体は、グールドが動かしているのかなっていうような、ものに憑かれたような悦楽 を感じて演奏している姿がそこにあって、やっぱり、学習と芸術の違いっていうのは、そこに真の喜び があるかないかという、そこにかかっているのかなと感じています。」
(3)青柳いずみこ(1950年生まれ・東京芸大卒・ピアニスト・エッセイスト・2011年『未来のピアニスト グレン・グールド』発刊)
「とことんゆっくり弾いてみたり、とことん早く弾いてみたり実験をしているんですけれども、どんなにデフォルメしても音楽本来の形が変わらない。崩さないって言うか。普通の才能がそういうことをすると音楽自体ががたがたになってしまうと思うんですけど、正統的な音楽性を持っていてその上でのデフォルメだったということが、素晴らしい指揮者とか演奏家たちには、そのことが分かったんじゃないかなと思います。」
(4)清塚信也(1982年生まれ・桐朋学園大卒・ピアニストだけでなく作曲家、編曲家、俳優でもある。)
同じくMCを務める鈴木愛理さんが、清塚さんにグールドのコメントを求める。
「皆さんおっしゃるには、オーソドックスから離れているという言い方は出来ない。そこで悦楽があると小山実稚恵さんがおっしゃってたけど、そこに喜びがあるからそのまま人に出すっていう 怖さを乗り越えた人 だと思うんだよね。」
結論 by 親爺
今のピアニストにとって、ピアノはレガートに弾けば弾くほど良い、3階席の観客までピアニッシモの音も届けるのがピアニストだと考えている間は、グールドのようにポリフォニーを自在に明確に弾き分け、スタッカートとレガートを同居させ、声部ごとに弾き分けるのは、非常に困難だと思う。
グールドを《同業者》と表現し、「練習を1日休むと自分で分かる。2日休むと批評家に分かる。3日休んだら観客に分かる。」と言ったポーランドの有名なピアニスト、パデレフスキの言葉を引用しながら説明をする青柳いずみこさんが告白するように、彼女の指は自在に動かない。それは他のピアニストも大なり小なり同じだ。高い椅子に座って腕を上方から振り降ろし、爆発するようなフォルテで大音響を出し、コンサートホールの観客を圧倒しようと考えるピアニストが、多声の曲の各声部を対等に歌わせる対位法的演奏をすることと、このような爆発的なフォルテを弾くことを両立するのはどうも無理だと思える。
また、グールドは、『ピアノは30分で教えられる』というトピックのインタビューで、「ムカデ[3] は、百本の足の動かし方を考えるのが嫌いです。能力を損なわれるからです。動かし方を考えるとまったく動けなくなるからです。」と言っている。ピアノの練習でも指使いに考えを持っていってはダメだというのだろう。「動作は、円滑かつ自動的に機能しなければならないが、それらに注意をしてはならない。」
また、こうも言っている。「ピアノに向かうよりもたっぷり前から曲目を知り、そして(あるいは)触感を超えた体験をする。そうすればピアノによるあらゆる干渉を抑えられるのです。・・・・完全性は、ピアノから離れてさえいれば理論的には獲得可能です。ピアノに向かった瞬間、触感上の妥協を強いられ、完全性の程度は下がります。そして妥協点を見つけることになりますが、理想を追求した分だけ妥協をしないで済むの です。」 決して、巷間よく言われるように《一生懸命繰り返し練習して、指使いを体に覚えこませる》というような方法で曲を弾こうとしないことだ。
グールドは、あらゆる曲を暗譜で弾いた。抽象的で、暗譜が難しいと言われるシェーンベルクなどの現代曲でも暗譜で弾いた。おまけに一緒に演奏する他の楽器の楽譜も暗譜していた。楽譜にまったく運死(指使い)を書かない。楽譜を見た瞬間に指使いが決まったという。グールド研究者が、楽譜に数字が書かれているのを見つけたら、それは知人の電話番号だったという。ペダルをほとんど踏まないので、ひんぱんに指を持ち替えながら弾く。これらのことは、多くのピアニストがしないことだと親爺は思う。
「グレン・グールド著作集」などの書籍を何冊も出した音楽評論家・編集者であるティム・ペイジは、次のように言っている。 「これまで10本の指を持つ者で、10本の指がそれほどまで見事に独立した生命を持つ者が、誰か今までにいただろうか?」 ”Has anybody ever possessed ten fingers with ten such marvellously independent lives?”, Tim Page
グールド研究の第1人者である宮澤淳一さんは、グールドは《クラシックの音楽家》ではないと言う。何故なら、王様は作曲家であり、演奏者は家来だと考える音楽界にあって、グールドは自分が王様だと考えているからだという。まったくそのとおりだと思う。
親爺は思う。クラシックの音楽家であろうとなかろうと、リスナーは、演奏される曲が持つ最大の魅力を伝えてくれる最良の演奏を聴いて、感動に浸りたいと思うだけである。
おしまい
[3] ムカデの話:「グレン・グールドは語る」(ジョナサン・コット 宮沢淳一訳 ちくま学芸文庫)の「ピアノは30分で教えられる」でシェーンベルクの言葉として、グールドが語っている。