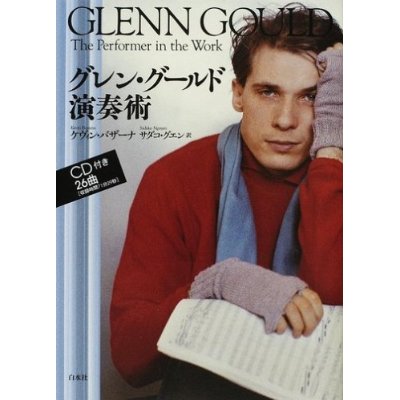グレン・グールドに関する書籍をさらに読んだので、感想第三弾。
【グレン・グールド演奏術】ケヴィン・バザーナ著 サダコ・グエン訳 白水社CD付 税抜き5,400円
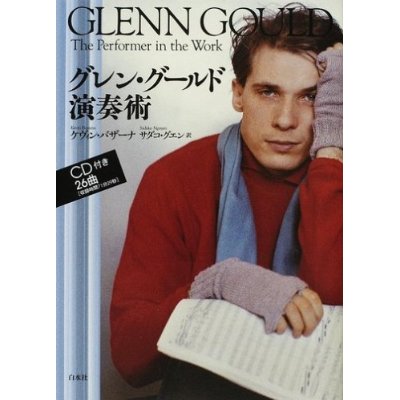 今回は大著だ。値段も高いが、ちょっと大き目の単行本で、グレン・グールドの演奏を楽譜とともに説明するためにCDがついている。原書は、ケヴィン・バザーナ(カナダ人。音楽ライターで音楽史と文学の博士号を持っている。)がカリフォルニア大学で書いた博士論文に手を加える形で1997年に出版され、日本語版初版は2000年に出版された。本書は、その新装版であり2009年に出版された。グールドの演奏の特徴や音楽に対する思考を中心にしたこれまで読んだ本の中で最大の大作だ。
今回は大著だ。値段も高いが、ちょっと大き目の単行本で、グレン・グールドの演奏を楽譜とともに説明するためにCDがついている。原書は、ケヴィン・バザーナ(カナダ人。音楽ライターで音楽史と文学の博士号を持っている。)がカリフォルニア大学で書いた博士論文に手を加える形で1997年に出版され、日本語版初版は2000年に出版された。本書は、その新装版であり2009年に出版された。グールドの演奏の特徴や音楽に対する思考を中心にしたこれまで読んだ本の中で最大の大作だ。
ケヴィン・バザーナは、映画「グレン・グールド 天才ピアニストの愛と孤独」でグールド研究者として登場し、グールドの様々な姿を紹介している。グールドは生涯独身をとおし、私生活を一切明らかにしなかったので、この映画が作られるまでグールドの女性関係は全くの不明だった。だが、この映画でケヴィン・バザーナは「女性観は、他の男と全く同じだ。」と何故か揶揄するように言っている。(もう少し、詳しく説明してほしいのだが、残念ながらそれはない。)
書かれている内容は一言で言ってしまうと、非常に深く掘り下げられていながら、バランスがうまく取れている。グールドの評価には常に賛否両論があるのだが、どちらの意見もうまく取り入れており、公平に書かれている。特にグールドの発言や意識は演奏と違い、本人が思っているほど彼自身のオリジナルでなかったり、レベルが高いものではなかった。また、グールドの演奏を具体的に楽譜で示し、オリジナルの楽譜とどのように違うのかを説明している部分もある。(この部分を理解するには楽譜が読めることが必要だ。残念ながら、CDをパプアニューギニアに持ってこなかったので、聴きながらこの本を読めなかった。もう一度読み返したいと思っているので、その時にじっくり吟味したい。)
他のメディアでも明らかにされているが、この本はグールドが他のピアニストと異なる点を非常に深く考察している。例えば、対位法に対するグールドの考え、すななち、複数の旋律を弾き分け、曲の構造を明らかにしようとする姿勢。どのような曲に対しても従来の演奏スタイルとは全く違うアプローチを検討し、独創的な演奏法を見出そうとする姿勢。(強弱やスピードなどの音楽記号を無視し!、反復しなかったり、独特の装飾法であったりする。)しばしば元の曲に手を加え、対位旋律を付け加えててしまうこと。演劇と映画の対比のように、コンサートとスタジオ録音を対比し、スタジオ録音では映画の編集をするようにテープを編集すること。
また、グールドの音楽の原点を次のように考察している。(ちょっと長くなるが容赦してほしい。)「・・その中のある二人の作曲家が、グールドのレパートリーで最も重要であり、音楽的価値のモデルと考えられている。バッハとシェーンベルクである。この二人はグールドの若いころから重要な作曲家であり、その作品はグールドの音楽の好みの中心を成していたのである。バッハはルネサンスとバロック期の正統な対位法の核であり、シェーンベルクは二十世紀の構造的に密度の高い音楽の核であった。しかし、この二人は重なり合ってもいたのである。つまりバッハは構造的に密な音楽の典型でもあり、シェーンベルクは対位法の模範でもあった。そして両者とも音楽に対する観念主義的姿勢の手本なのだった。」と書き、「数からいえば、バッハの作品の方がレパートリーの中心をなすものであるし、演奏習慣にも強い影響を与えたが、十代にゲレーロ(グールドを教えたチリ人ピアニスト)から学んだシェーンベルクの音楽と思想は、知的見地から言えば、より重要だったかもしれない。」「・・つまりグールドの考え方と演奏に非常に大きな影響を与えたバッハは、シェーンベルクの目を通して見たバッハという事になる。」たしかに、一理ある。
ところで、グールドは、モーツァルトの演奏は多くの批評家から酷評されるのだが、これについてもこの本で触れている。 具体的に紹介する前に、グールドのモーツァルト演奏をざっと説明すると次のようなものである。グールドはモーツァルトに対する評価をメロディーに対位法的な要素が少ないために、非常に低い評価しかしていない。モーツァルトの曲の展開部は展開していないなどといい、また、有名な曲ほどエキセントリックに弾く傾向がある。たとえば、トルコ行進曲で有名なピアノソナタK331では、近所の幼稚園児が弾くようなスタッカートで弾き始め、アダージョの指定のところをアレグロで弾いてみせる。トルコ行進曲は異常なゆっくりとしたスピードだ。こうした演奏を本書は次のように書いている「・・・ところがグールドの演奏といえば、音楽批評に挑戦、いや音楽批評を挑発しているのである。グールドは自らにふさわしいことは、モーツァルトを弾くことではなく、グレングールドのモーツァルトを弾くことだ、と他のどの演奏者よりも自分の役割を強く主張したのだった。そしてグールドの賛美者は、そうした態度に関心を寄せる人びとなのである。(グールドのレコーディングを聴いて、モーツァルトが「どう弾かれるべきか」を知ろうとするものはいない。)」「なぜグールドは、スウェーリンク( 1562年ー1621年。オランダの作曲家。バッハ直前の作曲家である。)やクルシェネック(1900年ー1991年。オーストリアの現代作曲家。)を称賛しながら、その作品をあまり演奏しなかったのか、そしてしばしば非難しながらもベートーヴェンやモーツァルトの作品を多く演奏したのか。これは後者はよく知られた、権威のある作品で、それゆえ挑戦すべき伝統や機会が多くあるからなのだった。」「私は、演奏者としてのグールドの業績は、単なる個々の演奏の集積以上の重要性があると信じる者である。なぜなら、グールドのさまざまな演奏の総体が論述と挑戦を意味するのであって、それは個々の演奏自体やそれぞれの演奏で具体的に表現してみせた知的な立場に対する評価とは、別個になされうるものだからである。たとえば、実に複合的なモーツァルトのレコーディングのような企画は、もちろんそれぞれのソナタや、作曲家についてピアニストが暗示する見解を吟味し、批評的な結果に達することが可能である。しかし同時に、それぞれのソナタの評価とは別に、あのモーツァルトの企画全体が演奏における拡大された批評的論述だと解釈できるのである。いや、それどころか、あの企画は、実際的な表現方法を用いて、このような論述が可能であることを示すモデルだと考えられるし、またそう考えた方が実りも多いのである。・・」非常に説得力のある分析だ。グールドが演奏する力は有り余って、自分が考えた正しいと思う演奏のほかにも、アンチテーゼともいえる演奏をも披露できたのだ。
ここで主は、モーツァルトのピアノソナタではなくピアノ協奏曲を1曲だけグールドが録音しているのを思い出した。どのように演奏しているのか気になって、改めてピアノ協奏曲26番を聴いてみた。
いやーすごい演奏だ!最初のピアノの導入こそおとなしいが、途中から低音のメロディーをガンガン鳴らし、ソロの部分はいろんな音を加えているようで、モーツァルトの協奏曲には聞こえない。悪くいえば破壊的、普通にいってエキセントリック、良くいって刺激的である。高音のメロディーより、中音部さらに異常な存在感の低音部が暴れまわる。途中で、思わず吹き出してしまった。他のピアニストのモーツァルトのピアノ協奏曲を知っていれば、驚愕するだろう。(クラシックファンでない人のために付け加えると、モーツァルトのピアノコンチェルトは、流れるような高音部のメロディーを美しく、哀しく楽しむのが普通。)だが、グールドのテクニックには他のピアニストにない気持ちの良いリズム、自由自在な音の長さと音の大きさからくる素晴らしさがあり、説得力がある。グールドの技量があまりにすごいので、荒唐無稽ともいえる演奏が曲の持つ新たな魅力を引き出している。この後、比較のためにYOU TUBEでアシュケナージの演奏を聴いてみた。アシュケナージはピアニストだけではなく指揮者としても有名な巨匠だ。しかし、こちらの演奏はいたってノーマルだが、退屈して途中で止めてしまった。今再び、グールドの演奏を聴いている。はるかに刺激的でこれはこれで面白い。寝た子も起きる新しいモーツァルトだ。
(ここからは、おまけ) グールドは10歳まで母親からピアノを習っていた。10歳からはチリ人ピアニストのゲレーロに習っていたが、ゲレーロにとってグールドはUnteachable な生徒だったという。このため、次のように本書に書かれている。「ゲレーロはかつて、グールドを教える秘訣は、何事でもグールド自身に発見させることだ、といったことがある。グールドに、ありふれた考えを、いかにも自分で考えついたように思わせるのはむずかしいことではなかった。しかしそうさせたからこそ、グールドはその考えを活性化できるのだった。」グールドは両親の教育方針でコンクールに出場するという事がなかった。コンクールに出場するという目標を与えられることなく、のびのびとピアノを弾かせたのである。この成果は非常に大きかった。先生のいう事を絶対視し、コンクールに出場するために型にはめられることがなかったのだ。(一方で、このことが、グールドの倫理観から競争という概念を排除した。コンサートを開かなくなったのもこの「競争」が関係している。)
ゲレーロはグールドにフィンガータッピングという奏法を教えている。フィンガータッピングというのは、指がピアノの鍵盤をはじいた時に自然に跳ね返る、この原理を利用してすべての指が独立して動かせるようになるまで修練するのだ。フィンガータッピングは他のピアニストで聞いたことがない、ゲレーロ独自のものだ。ゲレーロも非常に低い椅子に座って演奏したが、グールドもそうだ。一般的なピアニストは高い椅子に座り、姿勢を正しく背筋を伸ばし手の重みで弾く。フォルテは肩から腕に力を入れ、上の方から指を鍵盤に激突させて大きな音を出す。こうした奏法は、何千人も入るホールの後ろの客にも聞こえるようにするには必要なテクニックなのだ。しかし、フィンガータッピングではこのような衝突するような大きな音は出せない。しかし、非常に粒がそろった美しい音がだせる。また、自在に音量をコントロールすることもできる。グールドのフォルテは、このような爆音を出せないため、段丘状に音量を上げていき、フォルテを表現している。主は、グールドを聴きだしてから、他のピアニストの演奏を「何と乱暴な演奏だ!」と感じてしまう事が多くなった。他のピアニストは必ずこの指の落下により爆音をとどろかせる、これが原因だ。この奏法は確かに強烈な印象を与え、効果的な場面が実際にあるのだが、その効果は一時的で下手なピアニストはその後たいがいバランスを崩す。指を振り下ろした場合と鍵盤に指を添わせて弾く場合で、ギャップが大きいため中間的な音を出すのが難しいことと、曲全体の構造をよく考えていないのだ。また、感動の押し売りという感じがする。
グールドは、18歳で高校を中退している。しかし、彼の活動分野はピアノの演奏家だけでなく、著述業、指揮者、作曲家、ブロードキャスターとしても才能を発揮した。グールドは常に自分の意見を発信し続けたが、ピアノを離れるとやはりそこには限界があり、アマチュアといっても良かった。そうした方面でも才能は大きくあったのだが、評論家から強い反論やバッシングを受けていた。グールドはライナーノーツなども自分で書いていたし、音楽家として様々な著作を発表していたが、これらが否定されるとき、ピアノの演奏までも否定されることもあった。これに対し、グールドは主張を撤回するどころかますます強く主張し続けたが、メディアに対して徐々にひきこもるようななる。また、子供時代から薬を持ち歩いていたがこれが高じて、複数の医者から同じ薬を処方してもらい、薬物依存が進んでいく。また、ほとんど食事をとらず、睡眠もとらなかったという。
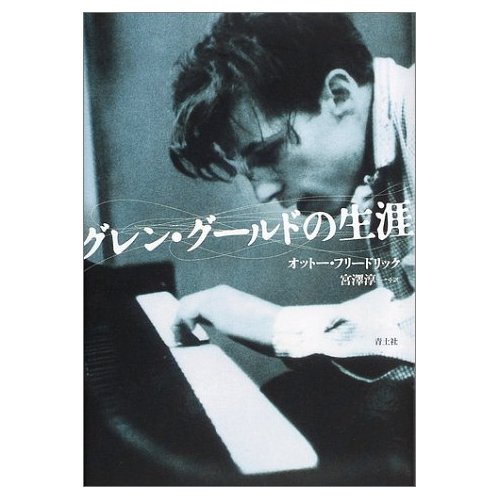 本書は、グールドの死後、グレン・グールド・エステイト(グールドの遺産を管理する法律事務所)が「公式」の伝記を作るためにアメリカ人ジャーナリストである著者に依頼したものだ。
本書は、グールドの死後、グレン・グールド・エステイト(グールドの遺産を管理する法律事務所)が「公式」の伝記を作るためにアメリカ人ジャーナリストである著者に依頼したものだ。