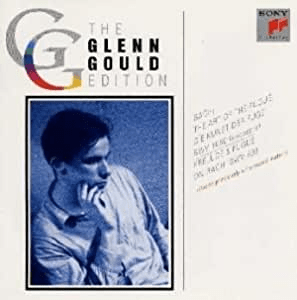——- 2023/9/2 タイトルを変えました。——-
グールドは、フーガの技法をオルガンとピアノで演奏したものの2種類を残している。オルガンの方は1962年5月に、この曲の前半半分(1番~9番)をコロンビアレコードから出した。ピアノの方は、グールドの死後である1997年に抜粋(1番、2、4、9、11、,13、14番=未完の終曲)が出されてているが、この2種類の演奏は、趣がまったく違っている。
ソニーの正規録音(発売時はコロンビアレコードだった。)で発売されているのは、オルガンの方で、ピアノの方は、死後に発売された《バッハ・コレクション》のCD34にフーガの技法(抜粋)とユーディ・メニューインとバッハのヴァイオリンソナタ第4番を入れたものや、オルガン版のフーガの技法とピアノ版のフーガの技法を入れたものがある。また、《坂本龍一セレクション》は、さすがに良い曲は網羅されており、オルガン版の演奏はなく、ピアノの第1曲と、未完の終曲の2曲がが収められている。
このオルガンとピアノの違いをさっくり書くと、オルガンは速い速度であっさり弾いている。グールドの友人のジョン・ベックウィズは、この演奏を「車のクラクションで『ゴッド・セイブ・ザ・クイーン』を鳴らす訓練されたアザラシのようなイメージだ」だと評したという。実際に車のクラクションで演奏したYOUTUBEを見つけたので、リンクしてみる。残念ながら、アザラシではなく、人間がホーンを鳴らしていますが。
他方、ピアノの演奏の方は、抑制的で、神秘的、深遠で、静謐、鎮魂的な雰囲気がたっぷりある。
このあたりのことは、親父のブログでも前に書いていたのでよかったら見てください。

前のブログで、いろいろなピアニストによるフーガの技法の演奏が、上の楽譜のとおり、アルトで始まりソプラノが入ってくる第4小節までどのように弾いているのか比べてみた。そうしたところ、グールドだけが、アルトとソプラノを右手1本で弾き、左手で指揮をしながら、バスが入ってくる第9小節まで左手を使っていない。
ブログで書いた福間洸太朗さんをはじめ、他のピアニストは、左手でアルトを弾き、4小節目のソプラノから右手で弾く人が多いようだ。前のブログには書かなかったが、アルトを右手で弾き、ソプラノがは入ってくると、手を持ち替えてソプラノをやはり右手で弾き、アルトを左手で弾く演奏者もおられるようだ。
こうしてみると、グールド以外の演奏者は、二つの声部を片手で弾かず、できるだけ両方の手を使い、とくに浮き立たせたいメロディーは右手で弾きたいように見受けられる。
ところで、逆にフーガの技法を、4手(二人の連弾)で弾かれている演奏を見つけました。この曲は、J.Cegledyという人によってアレンジされているようですが、エンディングのところなど、なかなか迫力があってデモーニッシュで、とても良い演奏だと思います。途中も、オクターブ上のメロディを足したり、かなり音数を増やしたように編曲されているように感じました。
さらにグールドおたくの親爺に言わせれば、グールドの演奏だけが、全体として、異常に思えるほど遅い。みなさん、基本的にさっさか、すたすた演奏するように思われる。遅い演奏をすることで、一音一音の意味が際立ってくるし、また、声部ごとの音量を強調したり、抑えたり、スタッカートで弾いたり、レガートで弾いたりすることで、独特の世界が見えてくる気がします。
また、このフーガの技法のテーマである第1曲で、グールドは他の演奏家が決してやらないことをやっています。最後の部分で、2度、全休止があるのですが、グールドは異常に長い休止をしています。ステレオが壊れたかと思うほどの長さです。こんな演奏をする人は他にいません。
あくまで親爺の意見に過ぎないのですが、音楽家という人種は、一般に『楽天家過ぎる!』と思っています。この弦楽四重奏やある程度の人数による弦楽合奏などの「フーガの技法」の演奏は、どの演奏家も、頑張って大きな音を出そうとしすぎ、存在を控えたり、消さなすぎだと思っています。ずっと、どの楽器も自分の務めを精一杯果たそうと、楽譜に書かれた音を出そうとするので音量を抑えられない。つまるところ、元気で明るい似たような曲ばかりができる。・・・と思います。
グールドと比べてみてください。(こちらのフーガの技法、あいにくちょっと録音の質がどうなんでしょう。)
このバッハの曲、とてもいい曲です、どの方の演奏を聴いても良い。飽きるということが決してありません。