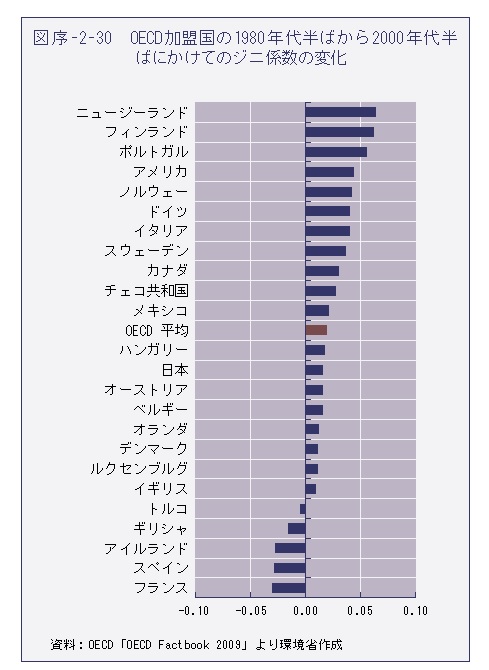ブラジルの話は帰国して10年以上がたち、ライブな話題を提供できないこともあって、ほとんど書かなかった。だが、トピックが全然ないわけではないので、なるべく軽くて、面白い話をしたい。
ブラジルに住んでいたのは、2002年から2006年までの4年間だ。主が住んでいたのは、首都ブラジリアだった。ブラジルと言えば、サンパウロ、リオデジャネイロ(リオ)が有名だが、ブラジリアは人工的に建設された首都で、当時建都45年くらいだった。そのため、人工的に設計された都市も、かなり老朽化が目立ち、近代的なのか、廃れているのか両方がミックスされた雰囲気があった。人口は、サンパウロ2,000万人、リオ500万人に対し、ブラジリアは周囲の衛星都市を合わせて当時200万人くらいだったように思う。他の都市には、立派な教会のある広場を中心としたセントロがあるが、ブラジリアにはこれといったセントロがなく、商業地域しかない。

赴任当初の2002年5月に日韓共催でサッカーのワールドカップが開かれ、ブラジルが5度目の優勝した。ブラジル国内は大騒ぎとなり、セレソン(ナショナルチーム)が凱旋パレードをした記憶が少し残っている。このセレソンは、ブラジリアを含むブラジル国内の主要都市を何か所か飛行機で巡ったのだが、パレードの予定時間が大幅に遅れ、最後のリオだかサンパウロでは、明け方、夜が白々と明けるころ行進し、「(時間にルーズな)ブラジルらしいなあ!?」と思ったのが懐かしい。
下の写真の1枚目は、リオのコルコバードの丘の有名なキリスト像。2枚目は、イパネマ海岸かコパカバーナ海岸といった有名な海岸をビキニ姿で歩く女性たちだ。このビキニは、タンガ(ブラジルビキニ)というのだが、上半身、下半身とも最小限の三角形で体を隠している。女性は年齢を問わず、このタイプの水着を着ている。
このような美しい海岸は、リオだけかと思うかもしれないが、ブラジルのこのような真っ白い砂、真っ青な空の美しい海岸は、赤道のあたりから温帯に入るアルゼンチンの手前までの数千キロにわたっている。
女性の服の話をすると、体の線を隠すのはダサく、体の線をはっきり出すのが恰好いいとみんな思っている。したがって、日本で一般的に着られる、体のラインを隠すゆったりした服は好まれない。スカートは、よっぽどでないかぎり普段は履かない。フォーマルなドレスの時には思い切り着飾り、スカートを着てハリウッド女優みたいな姿になるが、普段はGパンが一般的だ。
親爺らしく日本の説教臭い話題へ。外国から日本へ帰国する時にいつも思うのだが、女子高生が短いスカートを履き、化粧をしていると売春婦に見える。アニメの影響らしいが、どうかと思う。外国では、特にブラジルでは、前述したように女性は老いも若きも、体の線がはっきり出る服を好むが、TシャツにGパンという地味な格好が普段の姿だ。日本女性は、衣服と化粧品に対する嗜好やこだわりが非常に強いと思う。しかし、広告が成功しており、ある種の洗脳状態、強迫観念にかられているのだと思う。日本女性の支出の大きな部分はこの二つだろうが、ブラジルでは全体で見れば所得の高くない人が多いので、服装や化粧にかける金額はわずかだろう。


話を元に戻そう。ポルトガル語では海岸のことをプライアというのだが、このプライア抜きにブラジルを語れない。ブラジリアは内陸の首都のため、プライアがないことに住民は嘆く。だが、人造湖(ラゴ)があり、この水辺がプライアの雰囲気を少しだけ醸し出している。大西洋に面した本当の海岸線は、実に美しい。日本で有名な海岸は江之島だろうが、あんなに砂が黒くない。真っ白なのだ。空も、雲一つない真っ青な快晴のことがほとんどだ。気温もちょうどいい。日本人は赤道の近くは猛暑だと思っている節があるが、アマゾンの河口の州都ベレンであっても、ずっと日本より快適だ。ちょっと緯度が下がったバイア州の州都サルバドール(日本語にすると『救世主』になる)などでは、ブラジル全土でいえることだが、昔ながらのヨーロッパの風情のある建物が立ち並び、プライアで過ごす時間は何物にも代えがたい。

ブラジル人は、日本人のように海で泳ぐというケチなことはしない。プライアではビーチバレーをしたり、家族や仲間とお喋りをしながら、浜に寝そべって体を焼くのだ。パラソルの影の下のリクライニングチェアで、ビールやココナツジュースを飲むこともできる。このリクライニングチェアとビーチパラソルはレンタルなのだが、当時、1回100円くらいの金額で借りることだ出来た。お兄ちゃんが、スコップで砂を掘り、パラソルを立て、リクライニングチェアを設置してくれる。ブラジルは格差の大きな国なので、リクライニングチェアで寝そべっていると、さまざまな商品を売りに来るお兄ちゃんたちが、目の前を左右に行きかう。売られているのは、サングラス、サンオイル、つまみ類、雑貨など何でもありだ。
そのリクライニングチェアに寝そべり、サングラスの奥から、タンガ(ビキニ)姿の女性を何をするともなく、ビールなどを飲みながら半日くらい眺めていると、日本の満員電車で培われた人生観が変わっていくのが実感できる。脳みその構造が、プライアへ行って半日くらいすると組替わる。ケセラセラ、なるようになる、あくせくしても始まらない! と人生観が変わる。
ちなみに、ブラジル人に限らず一般に外国人が海で泳がないのは、一般の公立学校にはプールがないことが多く、水泳を習っていないからだ。ちゃん、ちゃん。
おしまい