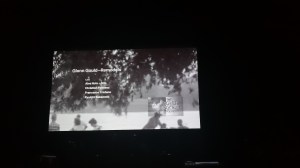日本は病気だと、主は確信している。日本の若者の6人に1人は、若者同士で恋愛できないほどの貧困にある。
米山新潟県知事が、2018年4月27日、出会いサイトで知り合った有名私大女子学生を買春していたと週刊文春にスッパ抜かれ辞職した。文春オンラインの次のリンクで冒頭の部分を読むことができる。「女子大生が告白 新潟県知事・米山氏「買春」辞任へ」
ネットの文春記事には、米山新潟県知事が、知事に当選する以前から1回3万円で女子大生の買春を始め、当選後には、知事当選を報告して、当選祝いとして単価を1回4万円へアップをしていたと書かれていたように思う。その米山知事なのだが、灘高から東大医学部を出て、在学中に弁護士資格もとり、医師資格も持っているとのことで、庶民からするとスバラシイ頭脳の持ち主なのだろう。(もちろん皮肉だが)
他方、このスキャンダラスな辞任会見と後のワイドショーなどを見た人は、3万円出せば有名大学の女子大生を買春出来ること、それが違法ではないことを知った人は多いだろう。「買春」は「売春」に該当するものの微妙に違うらしい。
同時に、主が驚いたのは、弁護士資格のあるこの男、新潟県知事に当選したことで嬉しくなり、それを女性に打ち明け、手当てを3万円から4万円へ増やしていることろだ。これは、知事の公職にある素性を買春相手に明らかにしていることを意味し、公人としての責任や社会的影響が理解できていないことを示している。また、その甘えが、週刊誌へのリークの動機になっていることは間違いない。
その後のメディアの報道は、他に大きな事件である北朝鮮の非核化、米朝対話、モリカケ事件、財務事務次官セクハラ事件などが続いたこともあり、深く掘り下げるむきは少なかったように思う。買春された側の女性の世間の受け止め方は、2チャンネルのような媒体をざっと見た感じでは、売春婦だのAV嬢だと単純な非難調なだけのようだし、主は、女性が被害者という報道は目にしていない。
だが、主が思う最大のポイントは、バブルがはじけて25年。格差が広がったことと、そのしわ寄せが若者にいっていることだと思う。
今の若者の中にも、当然格差があり昭和の時代と同様に、楽しく暮らしている若者も多いとはいえ、経済的な理由で若者同士で恋愛したり、あるいは、恋人と結婚することができないくらい、悲惨な状況におかれている若者も多いのだ。
大学生だけではない。とくに、地方から都会へ単身で働きに出てくる若者も、同じような状況がある。自分の出身地を離れて、都会で単身生活を送る学生や若者は、自宅通学(通勤)の学生(社会人)に比べると、月あたり10万円程度、家賃や光熱水費などで余分にかかる。ところが、学生の場合であれば、親からの仕送りが、親の世代の収入が昔より減っているため、ほとんどないかわずかのことが多い。社会人の場合は、給料水準が20万円以下ということがかなりある。この収入レベルだと、家賃などの支出に10万円かかるのは、大きく生活にのしかかる。
日本の貧困率は、少し前は7人に1人と言っていたが、今では、6人に1人と悪化している。例えば、1学級が30人のクラスなら、貧困状態にある生徒の数は5人である。この日本の貧困率はOECD加盟先進30か国の中で、下から4番目の悪さである。お隣の韓国よりも悪い。貧困率とは、ざっくり言うと、平均所得の中央値のさらに半分を言い、次のリンクが分かりやすい。【悪化する日本の「貧困率」】このリンクの説明によると、この貧困率は相対的貧困率なので、平均所得自体がバブル崩壊後の20年間以上低下しているので、名目値(絶対値)も下がっているはずだ。
多くの大学生は『奨学金』に頼るのだが、『奨学金』とは名ばかりで、実態は学生ローンだ。返済義務のない給付型の奨学金は絶望的に少ない。学生ローンを借りると、卒業時に数百万円の借金を背負うことになる。借りる奨学金を減らそうとすると、いきおい、学業よりアルバイトを優先することになる。これの同じ延長線上にあるのが、女子学生の「援助交際」だ。
「援助交際」を生活のためではなく、好んでやっているという見方があるのかもしれないが、それは偏見に満ちた考えだろう。時給の低いアルバイトより、割の良いアルバイトと考えていることはあるかもしれないが、「援助交際」という選択は、好んで選択しているのではなく、余儀なくされているのだ。若い女性が、好んでクソ親爺に抱かれたくはないだろう。
こうした異様な事態の背景に、日本中の就労形態でボーナスの出ない派遣社員だったり、官公庁や大学で働きながら「期限付職員」だったり「嘱託」が増えたという現状がある。公的セクターの施設の運営などで、コンセッション方式と言われる民間委託が導入されて久しい。しかし、その場所で働く労働者は、年功序列の恩恵を全く受けられない同じ賃金が続く。たとえば、市町村の図書館の運営は、コンセッション方式でTSUTAYAがやっていたりするが、契約は一定の期間ごとに入札されるので、働いている人の給料が上がることは期待できない。教員や研究者も、似たような状況が多く、正規雇用のシニアの教員や研究者は年功序列があるが、若者は期限付きの契約が多く、こうした契約の場合は、年限が来るとキャリアがリセットされてしまう。
コンセッション方式、PPP(Public Private Partnership)、PFI(Private Finance Initiative)などと言うと、なにやらもっともらしく響くが、実態はぜんぜん違う。公的セクターで行っていた切り取りやすい仕事を、民間のビジネスチャンスへと分け与え、儲けているのは請け負った会社の経営者であり、経費節減をしたと胸を張る官公庁の幹部だけだけだ。そこで働いている労働者は、同じことの繰り返しでスキルアップすることもないし、働き続けてもずっと低賃金のままだ。こうした低賃金で働く若者の存在は、正規で働く職員の賃金上昇にもブレーキをかける効果があるだろう。
結局のことろ、世の中はまやかしで蔓延している。25年間続いてきたデフレは未だに解消していない。現金を含む資産の値打ちは、25年前より上昇しているわけで、資産を持っている権力者や金持ちはデフレで困ることは一向に何もない。むしろ、値打ちの上がった資産効果により、女子学生を容易く合法的に妾にできる。「パパ活」という言葉もある。こうした金持ちは、大勢いるのではないかと透けて見えてくる。
NHKのテレビ小説「花子とアン」では、花子(吉高由里子)の華族で友人の「白蓮」(仲間由紀恵)が年の離れた好色な夫・伝衛門(吉田剛太郎)に苦しめられる様が描かれる。しかし、考えようによっては、明治の当時も今も、権力者や資産家が妾を囲っていることは暗黙の了解であり、ある意味責任と義務を果たしていた気が、主はする。女性の面倒だけではなく、子供の面倒などすべてを見ていたからだ。
日本病というにはインパクトがなかったかな?!(^^);;
ただ、今起こっているのは、ちょっと違うのではないか。1回3万円払って女子大生を買春するのと、妾を囲うのとでは、どこか趣が違う気がする。FACEBOOKが出会いアプリを始めたという報道がある。この違和感に近いものがある。「新しい恋愛」を「実名を出さず」、「友達に知られず」、「タイムラインに流れず」テンポラリーな恋愛を繰り返す事態は、これまでの家族観や家庭観が変る過渡期へと突入しはじめたのかもしれない。