人は異性(同性愛者なら同性でもいいわけだが)の人間性を認めて好意をもち、好きになり、うまく両者が同じペースで高まっていけば、愛しあうようになり、セックスへと続いていく。これが基本形。必ずしもこうしたプロセスを踏まず、短絡的だったり、見せかけ上だけで、内実は騙し、騙され、むしろ打算的、愛がないまま進むパターンも当然あるだろう。どちらのケースであっても、セックスをするようになるとそれまでとは様相が変わり、セックスが目的となり、大抵の場合、本末転倒する。好きだった人間性や、うわべを取り繕っていた(騙していた)ことなどが、脇へ置かれて、なかったも同然のこととなり、どこかへ忘れられてしまう。よく「手段と目的を間違える」という言い方をするが、セックスは、愛=コミュニケーションの手段で、出発点だったはずが、いつの間にやらそれ自体が目的となってしまう。結果として、目的となったセックスに、手段である愛=コミュニケーションがオマケのように小さくなる。
ここで果たして人間性を認めてセックスをするなら、何年たっても飽きないのだろうかという疑問がわく。人間性を認めて初めてセックスするとき、その時が最高点と言っていいだろう。だが、果たしてその最高点はずっと維持されるのだろうか。
「永遠の愛」などと言う表現があるが、何の努力もせずに愛が永遠に続くと考えるのは、甘ちゃんだと言われても仕方ないだろう。ネットで検索していると、恋愛感情はホルモンの分泌(フェニルエアチミン)と関係があり、恋愛の最初2,3年間は分泌され、その後減少してしまうとあった。
愛も、根本のところではGive and Takeだ。人間の欲望は果てしなく、手に入れたものは当たり前となり価値は減少する。このため、新たな価値を次々補給しないと、同じ愛情の大きさを長い間保ち続けられないだろう。
プラトニックな関係が続くのであれば、人間性を認めた付き合いが長い時間続きそうに思う。もちろん、時間の経過に伴い徐々に相手の評価は逓減するだろうが、急激には下がらないだろう。(例えば同性同士の友情を考えると、分かり易い。)ところが、セックスを始めてしまうと、減価償却のスイッチが入る。延命措置を施さないと耐用年数が来たところで残存価値が1割しか残らない。(会計学に詳しい人は、この言い方に納得してくれるかもしれない。)
おそらく、パートナーが変わらない場合、人間性に魅了されて毎回高まってセックスするという状態が続くことは稀だろう。だが現実には、多数の夫婦関係が生涯にわたって続く。理由の多くは、子供の存在が原因だったりする。パートナーへの愛情が減少しても、子供のために離婚しない「子は鎹(かすがい)」現象もあるだろう。また、離婚したくとも経済的な事情で選択しない、世間体を気にするケースも多々あるだろう。勿論、パートナーがベストだと思い続ける場合もあるだろう。「私はパートナーに隠れて不倫し、その罪悪感がパートナーへの愛情を高めている。」という人がもしいれば、それは矛盾ですぞ。
ここから先は、生物学的分析だ。もともと、人間の「好きになる」という状態から「セックスする」という流れは、文明や教育からインプットされたもので、動物として生まれつきのものではない。セックスを始めると、その動機を忘れてしまうというのも、生物学的にプログラムされたものではないからだ。当たり前だが、人間性を認めることとセックスの間には絶対的な関係はない。もう少し緩い関係だ。むしろ、主が住んでいるこの国、豚何頭かを提供すれば奥さんを貰えるというパプアニューギニアの村を考えると、人間性を認めてセックスするというより、セックスするようになって別の人間関係が開始されるように思う。
















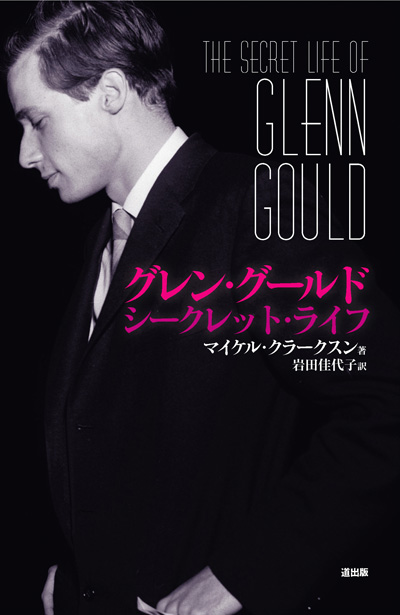
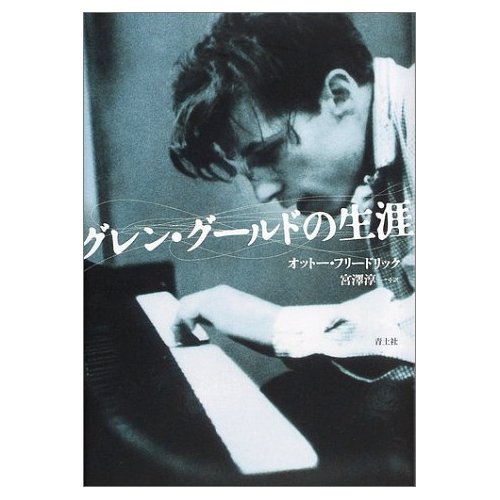







 上は学生たちの演技。男女がパフォーマンスを披露する。
上は学生たちの演技。男女がパフォーマンスを披露する。

 逞しい男。 頭を飾っているのは鳥の羽だろう。首から下がっているのは貝殻で造った首飾り。貝は昔、通貨だった。男が手にしているのは弓だ。
逞しい男。 頭を飾っているのは鳥の羽だろう。首から下がっているのは貝殻で造った首飾り。貝は昔、通貨だった。男が手にしているのは弓だ。



